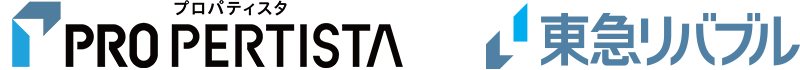専門家コラム
政策金利の今後の見通しと金融機関の優遇金利


COLUMNIST PROFILE
吉崎 誠二
不動産エコノミスト
社団法人 住宅・不動産総合研究所 理事長
ダウンロードDOWNLOAD
3月18日~19日に開催された日銀金融政策決定会合において、日銀は政策金利を0.5%のまま据え置くことを決定しました(19日午後発表)。
1月末の同会合では0.25%引き上げられましたが、今回の会合では据え置きとなりました。年内には1~2回の追加利上げが予測されています。
不動産投資において、多くの方が変動金利型の不動産投資ローンを利用しています。変動金利は政策金利の影響を受けるため、その動向は投資家にとって重要なポイントとなります。
日銀による金利操作の目的
中央銀行である日銀の大きな役割の一つは、物価を安定させることです。ここでいう「安定」とは、単純に物価が横ばいで推移することではなく、政府などと協議して定めた目標インフレ率に沿った動きを指します。
日銀の金利操作は、基本的に政策金利を引き上げたり引き下げたりすることを意味します。ちなみに、数年前までは固定金利に影響を与える長期国債の買い入れを行っていましたが、現在は市場への介入を減らしており(=買い入れ額を減額)、その影響を弱めています。
政策金利の調整は、物価動向(インフレ率)を見極めた上で行われます。インフレ傾向が顕著な場合は利上げを行い、逆にデフレ傾向が強まる場合は利下げを実施します。利上げによって需要を抑え、物価上昇を抑制するという仕組みです。日本では長期間にわたり物価の低迷が続いていたため、需要を喚起する目的で超低金利政策が維持されてきました。しかし、2022年以降は物価上昇が続き、2024年に入り、日銀はついに政策金利を引き上げる決断を下しました。
物価上昇の状況
物価上昇が顕著になり始めたのは、2022年春ごろからです。前年同月比で1%、2%、3%と上昇が進み、2023年初頭には約4%のインフレとなりました。その後、上昇幅は徐々に縮小し、2024年後半には2%台半ばで推移しています。日銀は、おそらく2022年から2023年にかけて「物価上昇が一時的なものかどうか」を慎重に見極めていたと考えられます。そして、2024年に入り、2013年以来掲げていた「安定的に2%程度の物価上昇」が続くと判断し、「2%を大きく超えないように」との方針のもと、0.25%~0.5%のわずかな利上げを実施したということでしょう。
インフレ率の見通し
日銀は年に4回(1月・4月・7月・10月)、「展望レポート」を公表し、その中で今後のインフレ率の見通しを発表しています。
過去のデータを振り返ると、2024年のインフレ率(コア・前年比)の見通しは1.9% → 2.4% → 2.8% → 2.5% → 2.7%(最後の数値は2025年1月公表分)と推移しており、直近2回のレポートではインフレ見通しが上方修正されました。
また、2025年のインフレ率の見通しも1.8% → 1.9% → 2.1% → 2.4%と、過去4回の発表で一貫して上方修正されています。さらに、2026年のインフレ率の見通しも1.9% → 1.9% → 2.0%(過去3回公表)と上昇しています。この推移を見ると、日銀の想定よりもインフレ率がやや高めに推移している状況がわかります。そのため、今後も政策金利が引き上げられる可能性があると予想する声が多いのです。

政策金利は今度上がるのか?
先述のとおり、2025年のインフレ率の見通しは現時点で2.4%となっています。しかし、今後の賃金動向や4月以降の物価上昇の状況次第で、見通しが変わる可能性は十分に考えられます。大手企業を中心に賃金の上昇が順調に進んでおり、人手不足による人件費の上昇傾向も顕著です。これらの要因を踏まえると、今後も物価上昇は避けられないと考えられます。そのため、年内に政策金利が引き上げられる可能性は高いでしょう。では、それはいつ頃になるのでしょうか? あくまで予想ですが、決算発表や賃金上昇のデータが出揃う6月または7月の日銀金融政策決定会合で、利上げが実施される可能性があると考えられます。
金融機関のローン獲得競争
変動金利の上昇は、「政策金利の上昇 → 短期プライムレートの上昇 → 変動金利の上昇」という流れで進みます。しかし、直近の金融機関の貸出金利の動向を見ると、必ずしもこの流れに単純に連動しているわけではありません。
その背景には、金融機関の「不動産投資ローンや住宅ローンを獲得したい」という思惑があります。企業の資金調達手段が借入(デッドファイナンス)以外にも多様化しているため、金融機関は貸出先の確保に苦戦しています。一方で、比較的安定した需要のある不動産投資ローンや住宅ローンの新規借入や借り換え顧客を獲得しようとする競争が激化しているのです。
どんな企業に金融機関は金利優遇をするのか
政策金利の上昇に伴い、既に融資を受けている案件の金利は連動して上昇しています。しかし、その一方で、前述のような背景から、新規の融資においては政策金利の上昇分をそのまま借入金利に転嫁せず、基準金利(店頭金利)を引き上げたとしても、その分、優遇金利の幅を拡大し、実質的な金利上昇を抑える金融機関も多く見られます。
ただし、すべての融資案件が一律に扱われるわけではありません。案件数が多く、信用力の高い大手企業(例えば、東急リバブルのように流通取り扱いが多い企業)からの融資案件や、融資を受ける個人の信用度によっても金利が左右されるようです。
現在、金利は上昇傾向にあるものの、「どの企業を通じて物件を購入するかによって借入金利が変わる時代になってきた」と考えておくとよいでしょう。
- ご留意事項
- 不動産投資はリスク(不確実性)を含む商品であり、投資元本が保証されているものではなく、元本を上回る損失が発生する可能性がございます。
- 本マーケットレポート に掲載されている指標(例:利回り、賃料、不動産価格、REIT指数、金利など)は、
不動産市場や金融市場の影響を受ける変動リスクを含むものであり、これらの変動が原因で損失が生じる恐れがあります。
投資をする際はお客様ご自身でご判断ください。当社は一切の責任を負いません。 - 本マーケットレポートに掲載されている情報は、2025年4⽉16⽇時点公表分です。
各指標は今後更新される予定があります。 - 本マーケットレポートに掲載した記事の無断複製・無断転載を禁じます。