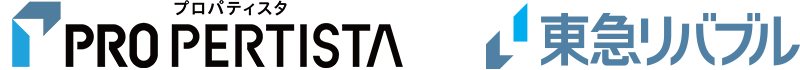専門家コラム
人口動向から見る首都圏物件への投資の優位性


COLUMNIST PROFILE
吉崎 誠二
不動産エコノミスト
社団法人 住宅・不動産総合研究所 理事長
ダウンロードDOWNLOAD
4月14日に総務省から2024年10月1日現在の日本の人口が発表されました。
これによれば、日本の総人口は1億2380万2千人で、前年に比べ55万人(-0.44%)減少、14年連続の減少となりました。日本人だけでみれば、1億2029万6千人で、前年に比べて89万8千人(-0.74%)減少、22-23年では83.7万人の減少でしたので減少幅が拡大(13年連続)しました。
都道府県別では、人口増加は東京都と埼玉県の2都県のみ(昨年は東京都のみ)で、東京都の人口増加率は0.66%で前年よりも増加率は大きくなりました。人口の増減は不動産市況に大きな影響を与えることは言うまでもありません。ここでは、最新の人口動向について解説します。
日本人の人口減少ペース拡大
2023年から2024年にかけての人口減少は、約89.8万人に達しました。10年前(2014年→2015年)の日本人の人口減少数は約24.3万人でしたから、減少幅が急速に拡大していることがわかります。現在の傾向が続けば、2026年の結果(2027年春に公表予定)では、日本人の年間減少数が100万人を超える可能性もあります。
人口減少が拡大し続けている背景には、出生数の減少と、死亡者数の増加という二重の要因があります。ここ数年を見ても、日本人の人口は大きく減少しているものの、外国人の流入によって年間約30万人が増加しており、その結果、全体の人口減少はおおよそ50万人程度にとどまっている状況です。日本の人口は1967年(昭和42年)に初めて1億人を突破し、その7年後の1974年には1億1,000万人、さらに10年後の1984年には1億2,000万人を超えました。最終的に人口がピークを迎えたのは2008年で、1億2,808万人に達しています。
ちなみに、人口のボリュームゾーンを形成する団塊世代は、1974年には25〜29歳、1984年には35〜39歳、そして2008年には還暦を迎える年齢に差し掛かっていました。日本の人口の増減は、まるで団塊世代のライフサイクルと重なるようにも見えます。
人口減少の背景
人口の増減には、「自然増減」と「社会増減」の2つがあります。自然増減は出生数と死亡者数の差によるものであり、社会増減は国内外の人の移動による増減を指します。
2024年の出生数は71.7万人で、前年より約4.1万人減少しました。2000年以降を見ると、出生数は一貫して減少傾向にあり、2000年は119.4万人、2016年が最後の100万人超え(100万400人)となっています。つまり、この8年間で出生数は約30万人も減少したことになります。
少子化対策は今のところ目に見える成果を上げておらず、2025年には出生数が60万人台に、2030年には50万人台にまで減少する可能性も出てきています。一方、死亡者数は2024年に初めて160万人を超え、160万700人となりました。今後は団塊の世代が後期高齢者となるため、平均寿命を考慮すれば、死亡者数はさらに増加していくと予想されます。その結果、人口の自然減もますます拡大していくことは確実です。
今や、日本では毎年、政令指定都市1つ分の人口が減少している状況になってきたのです。
年齢区分別人口
15歳未満の人口は1,383万人で、前年から34.3万人の減少となりました(前年は32.9万人の減少)。総人口に占める割合は11.2%で、過去最低を記録しています。15〜64歳のいわゆる生産年齢人口は7,372.8万人で、前年より2万4,000人減少し、総人口に占める割合は59.6%となりました。
一方で、これまで増加が続いていた65歳以上の人口は3,624.3万人に達し、総人口に占める割合は29.3%と過去最高を更新しました。また、75歳以上の人口は2,077.7万人で、総人口に占める割合は16.8%となり、つまり「6人に1人」が75歳以上という計算になります。
総人口の約3割が65歳以上という「世界一の高齢化社会」と言われるのも納得の状況です。
また、15歳未満の割合11.2%は、韓国の10.6%に次いで世界で2番目に低く、65歳以上の割合29.3%は他国を大きく引き離して世界1位です。2位はイタリアの24.6%で、先進国では高齢者人口の割合が10%台後半から20%程度にとどまる国が多い中、日本の高齢化の進行は突出しています。

都道府県別の人口
都道府県別に見ると、最も人口が多いのは東京都で、1,417万8,000人(前年比0.66%増)となり、全国総人口に占める割合は11.5%となっています。東京都の人口増加率は、前年が0.34%、前々年が0.20%だったため、増加のペースが加速していることがわかります。
人口の多い都道府県の順位に大きな変動はなく、2位は神奈川県(922万5,000人)、3位は大阪府(875万7,000人)、4位は愛知県(746万人)、5位は埼玉県(733万2,000人)、6位は千葉県(625万1,000人)となっています。なお、この6都府県のうち、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の「首都圏1都3県」に限ると、全国総人口に占める割合は29.9%に達しており、全国のほぼ3割が首都圏に集中している計算になります。
都道府県人口変動の要因と生産者人口の割合
都道府県別に自然増減を見てみると、自然増となっている都道府県はひとつもありません。2021年まで唯一自然増が続いていた沖縄県も、2022年以降は自然減に転じており、その減少幅も年々拡大しています。東京都や埼玉県のように人口が増加している地域でも、自然減の状態が続いており、社会増(転入超過)によって全体の人口が増加しているという構図です。都道府県をまたぐ移動が要因となる社会増減を見ると、22の都道府県が社会増となっています。なかでも社会増加率が高い上位5都府県は、東京都・埼玉県・大阪府・千葉県・神奈川県で、特に首都圏(1都3県)への人口流入が引き続き顕著です。
先述のとおり、15~64歳の生産年齢人口の割合は全国平均で59.5%ですが、この割合が60%を超えているのは7つの都府県のみです。該当するのは、首都圏(1都3県)に加え、大阪府・滋賀県・沖縄県であり、若年層の流入が続いている地域と言えます。
人口動向と賃貸住宅需要
日本人の総人口が減少するなかで、首都圏(1都3県)への人口流入は一層顕著となっており、都市部への人口集中が進行していることが明らかです。
大阪府の人口はわずかに減少したものの、社会増(転入超過)の数は増加しています。大阪を含む1都3県では、生産年齢人口の割合が6割を超えており、社会増による人口維持が特徴的です。
こうした状況から見ると、日本全体としては人口が減少していても、首都圏では賃貸住宅への安定した需要が継続しているといえます。そのため、首都圏の不動産市場は依然として投資対象としての魅力を保っていることが分かります。
- ご留意事項
- 不動産投資はリスク(不確実性)を含む商品であり、投資元本が保証されているものではなく、元本を上回る損失が発生する可能性がございます。
- 本マーケットレポート に掲載されている指標(例:利回り、賃料、不動産価格、REIT指数、金利など)は、
不動産市場や金融市場の影響を受ける変動リスクを含むものであり、これらの変動が原因で損失が生じる恐れがあります。
投資をする際はお客様ご自身でご判断ください。当社は一切の責任を負いません。 - 本マーケットレポートに掲載されている情報は、2025年5⽉16⽇時点公表分です。
各指標は今後更新される予定があります。 - 本マーケットレポートに掲載した記事の無断複製・無断転載を禁じます。