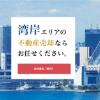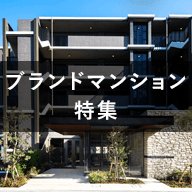タワーマンションの特徴とメリットとは?魅力と注意点を徹底解説

ざっくり要約!
-
タワーマンション(タワマン)は、一般的に20階以上の高層マンションを指し、そのメリットには土地の有効活用、経済的な好影響、コミュニティの形成、エコロジカルなアプローチ、防災機能の向上、地域活性化が含まれる。
-
一方、デメリットにはエレベーターの混雑、高い管理費、地震時の不便さ、洗濯物を干せないこと、大規模修繕の負担、ライフラインの問題がある。
-
タワーマンションは、利便性と快適性を高める要素が多く、都市生活を支える重要な住宅形態である。
近年、タワーマンション(タワマン)は日本の都市景観に欠かせない存在となり、特に都市部ではその人気が高まっています。しかし、タワーマンションの定義やメリット・デメリットについては、あまり知られていないことが多いです。本記事では、タワーマンションの具体的な定義やその利点と欠点について詳しく解説し、現代の都市生活におけるタワーマンションの役割を考察します。
目次
タワマンの定義やメリット
近年タワーマンション(通称タワマン)という言葉は、日本の都市景観の中でポピュラーなものとなっていますが、その具体的な定義や基準についてはさまざまな意見や解釈があります。一般的には、タワーマンションは20階以上の高層マンションを指すことが多いです。
タワーマンションの定義と基準
タワーマンションの定義には明確な法律や規制が存在するわけではありませんが、一般的には20階以上のマンションを指しています。この20階という基準はあくまで目安であり、地域や国、施工業者によって異なる場合があります。
タワーマンションのメリット
タワーマンションのメリットとしては下記のようなものが挙げられます。
土地の有効活用
タワーマンションは、限られた土地を最大限に活用するために有効な手段です。特に都市部では土地の価格が高価であり、だれもが一戸建てを建てられるという状況ではありません。よって、地価が上昇する中で、縦に伸びる高層建築は有効な土地利用方法となります。高層建築を採用することで、同じ敷地面積に多くの居住空間を提供できるため、土地の効率的な活用が可能です。これにより、人口密度の高い都市部での居住スペースが拡大され、住戸不足が改善されます。
経済的な好影響
タワーマンションの建設によって、多くの経済的なメリットが発生することが考えられます。建設時には、建設業や関連業界への需要が高まり、地元の雇用創出につながります。そして、建築に関わる人たちがその街を利用するようになると、飲食店などは従来の顧客以外の取り込みも可能となり、売り上げアップにもつながるでしょう。
また、完成後は大幅に住民が増えるため、地域の経済活動が活性化。賑わう街には多くの人が訪れるようになり、二次的、三次的な効果が期待できます。
コミュニティの形成
タワーマンションは、その規模からコミュニティの形成に寄与することがあります。フィットネスジムやラウンジ、キッズルームなどの共用施設には、住民が集まり、顔見知りになれば自然と挨拶をする仲に。何度も挨拶を交わすようになると、それぞれが自然に交流する機会を生み出し、地域社会の一体感を高めることができます。また、管理組合や住民協議会などの組織を通じて、住民の意見を反映させたコミュニティ活動が促進されているタワーマンションもあるようです。
エコロジカルなアプローチによる、持続可能な都市生活の実現
近年のタワーマンションでは、環境に配慮した設計が増えています。グリーンビルディングやエコロジカルな建築技術を取り入れることで、省エネルギーや資源の効率的な利用が実現されています。例えば、太陽光パネルで蓄電した電気を共用部分で使ったり、貯めた雨水を植栽の水やりに使ったりなど、大規模だからこそ叶うエコロジカルなアプローチにより、持続可能な都市生活が推進されています。
インフラの整備が進む
タワーマンションの多くは、交通機関や商業施設にアクセスしやすい立地に建設されることが一般的です。再開発前などでインフラが乏しい場合は、マンションの建設と同時に、周辺のインフラが整備されるケースも多くなっています。タワーマンションの周辺に新たな公共施設や公園が整備されることもあり、地域住民の生活の質が向上します。
防災機能の向上
タワーマンションの設計には、防災機能が組み込まれています。最新の耐震技術や避難設備が整備されており、大規模な自然災害に対しても一定の耐性を持つことができます。また、タワーマンションの建設には、防火対策や防犯対策が徹底されており、住民の安全を確保するための取り組みが行われています。これにより、マンション全体の防災能力が向上します。
地域活性化
タワーマンションの建設は、地域の活性化にも寄与します。新たな住居の提供だけでなく、商業施設やレストラン、カフェなどが誘致されることが多いです。これにより、地域の商業活動が活性化し、地元経済が潤うことがあります。
豊洲エリアは、タワーマンションの建設ラッシュに伴い、2000年代に入ってから小学校が2校開校しました。人口に占める子どもの割合が減り、閉校や合併する学校のニュースが多く聞かれるようになって久しい中、この事例は明るいニュースと言えます。未来を担う子どもたちが増えることで、地域が活性化していくことが期待できるでしょう。
タワーマンションとは? 定義はあるの?
冒頭でもタワーマンションの定義について少しお話をしましたが、こちらではより詳しく説明していきます。
タワーマンションとは、一般的には20階以上の超高層マンションを指す
一般的な定義
タワーマンションと似たものに「高層マンション」があります。これは、高さ31ⅿ(10階以上)を超えるマンションを指すことが一般的。31ⅿを超える高さの建物は、消防法第8条の3第1項において「高層建築物」として定義されています。よって、この概念から31ⅿを超える高さの建物は高層マンションと呼ばれているようです。
一方タワーマンションは、20階以上のマンションを指すことが多くなっています。こちらも明確な定義や法律による定めはありませんが、建築基準法20条において高さ60mを超える「1号」建物を超高層建築物と位置付けていることから、この概念を用いて20階以上をタワーマンションと呼んでいるのが通例となっています。
タワーマンションは、躯体や基礎、建物構造までが地震や強風への耐性が高いなど、綿密に計算された堅牢な造りになっている点も特徴です。
超高層建築物には国土交通大臣の認定が必要
建築基準法では高さ31メートル超の高層建築物、60メートル超の超高層建築物に対し、その高さによって段階的に建築基準が適用されています。つまり、60メートル超の一般的にタワーマンションと呼ばれるマンションは、建築基準法上、最も厳しい基準が適用されて建っていることになります。建築基準に達していないと、いくら素晴らしいコンセプトを掲げていても認定が下りず、建築に進むことはできません。
具体的には、定められている構造計算方法を用いて、地震波や強風時における振動現象のシミュレーションを実施します。ここで、基準値を達成することで、国土交通大臣の認定を受けられます。
この認定を受けたタワーマンションは、震度6強から7の地震発生時に、高さに対する揺幅が1/100以内になるよう設計されています。例えば高さ100mのタワーマンションであれば、振幅1mを越えないように設計しているというわけです。
さらに、高層建築物にあたる高さ31メートル超のマンションの場合、保有水平耐力計算や限界耐力計算などの高度な技術的基準に適合しなくてはなりません。タワーマンションには安心・安全に暮らすための厳しい基準があって、その上でそれぞれのコンセプトやデザインが成り立っていることになります。
さらに、タワーマンションでは必須の設備であるエレベーターの設置基準も設けられています。地震発生時には、震度ごとに基準が決まっていますが、具体的には下記のような内容です。
- 震度6強から7の地震発生時:かごが脱落しない
- 震度5弱程度の地震発生時:直ちに停止
- 震度4程度の地震発生時:最寄りの階へ移動して着床。乗客が避難できるよう設計
また、タワーマンションでは火災の発生を想定した消防設備の設置、避難経路の確保も評価項目となります。
非常用エレベーターの設置
タワーマンションだけでなく、31m以上の高層マンションも対象となります。これは、多くのはしご車が届く高さの限界が31ⅿほどであるためです。それ以上の建物の場合、消防隊員が迅速に高層階へ向かい、消火や救出活動が行えるようにと決められた基準です。
防炎物品の使用
こちらも31ⅿ以上の建物が対象。高層の建物は、低層の建物に比べて避難や救出活動に時間を要します。この背景による被害を最小限におさえるために、使用するカーテンやじゅうたんなどは防炎物品にしなくてはなりません。これは高層階だけでなく、すべての階が対象です。
高さ100m以上の場合はヘリコプターの「緊急離着陸場」を設置
火災発生時、高層階の住民が空からも避難できるよう、ヘリコプターの「緊急離着陸場」を設置することが決められています。これに該当する建物は、屋上にHのマークが記載されています。
ちなみに、高さ45m以上100m未満の建物は、ヘリコプターが着陸できなくても構いませんが、ホバリングしながら救出活動を行えるよう「緊急救助用スペース」を設けることが要請されています。この建物には、屋上にRのマークがついています。HやRのマークは、ヘリコプターが高所からどのような建物なのかを見分けるために必要な印ということです。
認定を受けたタワーマンションは、これらの厳格な基準を満たしているため、安全性や品質が保証されています。住民にとっては、安心して暮らせる環境が整っているという大きなメリットがあります。
タワーマンションに住むメリットは?

ここではタワーマンションに住むメリットをご紹介していきます。
日当たりや眺望が期待できる
タワーマンションに住む際の最も大きなメリットの一つは、その優れた日当たりと眺望です。高層階に住むことで、以下のような利点があります。
-
豊富な自然光
高層階に住むことで、周囲の建物による影響が少なく、自然光を豊富に取り入れることができます。室内は常に明るく、快適な居住環境が実現します。 -
素晴らしい眺望
高層階からの眺望は圧巻で、都市の夜景や自然の美しい景色を一望できます。特に夜間の都市の灯りや、晴れた日の青空は、生活に彩りを与えるでしょう。 -
静かな環境
地上の騒音や交通の音から距離があるので、比較的静かな住環境が提供されます。リラックスした、自分時間を過ごせるでしょう。
共用施設やセキュリティが充実
タワーマンションでは、共用施設やセキュリティの充実が見られます。これにより、住民の生活がより快適で安全に保たれます。
-
共用施設の充実
多くのタワーマンションは、住民の生活を豊かにするために様々な共用施設を備えています。例としては、フィットネスジム、プール、サウナ、シアタールーム、ラウンジ、キッズルームなどがあります。 -
ホテルライクなサービス
エントランスの車寄せ、コンシェルジュサービスなど、ホテルに訪れたようなサービスを提供している物件が多いです。内廊下やポーチ付きの住戸など、プライバシーに配慮されているマンションも見受けられます。 -
セキュリティの充実
多くのタワーマンションでは、24時間体制で管理人や警備員が常駐し、人の目でマンションを監視しています。また、共用部には監視カメラを設置し、不審者の侵入などをチェック。オートロックシステムは1段階ではなく、2段階、3段階というのも珍しくありません。
利便性や快適性がアップ
タワーマンションの立地は、その利便性と快適性を高める要素となります。都市部に位置することが多いため、以下のような利点があります。
-
アクセスの良さ
多くのタワーマンションは都市部に位置し、駅やバス停が近くにあります。これにより、通勤や通学がスムーズで、移動が楽になります。交通機関のアクセスが良好であることは、日常生活の効率を高める重要な要素と言えるでしょう。また、娯楽、文化施設へのアクセスも良好なケースも多く、遠くへいかなくてもさまざまな文化に触れられる機会にあふれています。 -
商業施設や飲食店が豊富
都市部に位置することで、買い物や外食に不便を感じることはあまりないでしょう。再開発とともにショッピングモールや飲食店が徒歩圏内にできることも多くなっており、利便性向上や時間の節約ができる生活が実現できるでしょう。 -
快適な生活環境
高層階からの眺望や広々とした共用施設、充実したセキュリティなどがそろい、住民は快適な生活を享受できます。特に広々としたバルコニーや庭付きの物件では、プライベートな時間を充実させることができます。
タワーマンションの「眺望」に関する記事はこちら

夜景がきれいなタワーマンションの選び方は? 選ぶポイントや注意点を解説
夜景がきれいなタワーマンションに住みたいと考えている場合、どのようなポイントで選べばいいか気になる人は多いでしょう。タワーマンションだからといって、必ずしもきれいな夜景が楽しめるわけではない点に注意が必要です。本記事では、夜景がきれいなタワーマンションを選ぶときのポイントや、注意点を解説します。
タワーマンションの「間取り」に関する記事はこちら

タワーマンションの間取りの特徴は?
高級マンションの代名詞ともいえる「タワーマンション」。その間取りが気になるという方も多いのではないでしょうか。本記事では、タワーマンションの間取りの特徴やよく見られる間取りについて解説します。
タワーマンションのデメリットは?
ここでは、タワーマンションのデメリットについて見ていきましょう。
エレベーターの混雑
高層階に住む場合、エレベーターの利用は必須。そのような中、特に朝の出勤時間や通学時間帯は混雑や待ち時間が問題となるケースがあります。エレベーターの混雑は、日常生活におけるストレスの原因となることがあります。
管理費が高い傾向にある
タワーマンションのメリットの一つに共用施設の潤沢さが挙げられます。しかし、共用施設が多いということはその管理にも費用がかかるということになります。また、規模が大きいマンションほど、共用部の電気代、水道代がかかることは念頭に置いておきましょう。
最近はこういった点を回避するために、太陽光パネルの設置や雨水の蓄積によって、共用部分の電気使用量や水道使用量を減らしているタワーマンションもあります。
地震発生時の不便さ
タワーマンションは厳しい建築基準法をクリアして建てられているので、大きな地震が発生しても、建物が倒壊したり、住めなくなってしまうような損害を受けたりすることはないと考えていいでしょう。
しかし、地震発生時には、エレベーターが使用できなくなってしまうケースがあります。これは故障というより、非常時の安全を確保するために停止してしまうというケースです。
よって、非常階段を利用しないと地上に出られないことがある点も想定しておく必要があるでしょう。特に高齢者や身体に障害を持つ人々にとって、これは大きな課題となることがあります。
入居したら、タワーマンションに住んでいることを意識しながら避難経路を確認し、マンションの管理組合が実施する防災訓練にはできる限り参加するようにしておくと安心でしょう。
外に洗濯物や布団が干せない
高所から洗濯物が落下すると、思わぬ被害につながってしまうことがあります。車のフロントガラスへの落下、線路への飛来などの発生は可能性がゼロではありません。タワーマンションによってはこのようなことを想定し、外へ洗濯物や布団を干すことを禁止しているところもあります。また、景観が損なわれるという理由から洗濯物が干せないケースもあるようです。
大規模修繕の費用負担が大きく、期間が長くなる
タワーマンションの大規模修繕には、通常のマンションに比べて費用負担が大きくなる傾向があります。これは、建物の高さや規模が大きいため、修繕作業の範囲や難易度が増すからです。
また、大規模修繕には時間がかかる場合があります。修繕作業が行われる期間中は、住民が一時的に不便を感じることがあります。
停電などライフラインが止まったときの準備が必要
タワーマンションでは、停電やライフラインの停止が発生する可能性があります。特に高層階では、停電時にエレベーターが使用できなくなるため、非常用のライトや発電機、数日分の食料、水の備蓄をしておくと安心でしょう。
多くのタワーマンションでは、マンションとして非常時の備蓄をしているところもありますが、それが1階などの低層階のみに設置されているケース、数階に1カ所と複数カ所に設置されているケースとさまざまです。マンションの備蓄とは別に備えておくと安心です。
タワーマンションの「メリット・デメリット」に関する記事はこちら

タワマンに住むメリット・デメリットとは? 高層階…低層階ならではの魅力も解説
タワーマンションは、その立地の良さや利便性の高さで高い人気を誇りますが、住む前に知っておくべきメリットとデメリットがあります。本記事では、タワーマンションならではの魅力をはじめ、移住する際に注意したいポイントを紹介します。
まとめ
タワーマンションは、多くのメリットを提供してくれる、忙しい現代人にとって理想的な住まいです。日当たりや眺望の良さ、充実した共用施設、優れたセキュリティなどがそろい、生活の質を向上させる要素が豊富です。一方、エレベーターの混雑や大規模修繕の費用、ライフラインの停止による不便さなどのデメリットが存在することは認識しておく必要があります。
タワーマンションを検討する際には、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、自分のライフスタイルに合った物件を選ぶことが重要と言えるでしょう。
Q. タワーマンションにはどんなメリットがありますか?
A.タワーマンションのメリットには、土地の有効活用、経済的な好影響、コミュニティの形成、エコロジカルなアプローチ、インフラの整備、防災機能の向上、地域活性化が挙げられます。詳しくは「タワーマンションのメリット」をご覧ください。
Q. タワーマンションに住むことのメリットは何ですか?
A. 日当たりや眺望の良さ、共用施設やセキュリティの充実、利便性や快適性の向上があります。詳しくは「タワーマンションに住むメリットは?」をご覧ください。
Q.タワーマンションのデメリットには何がありますか?
A. エレベーターの混雑、管理費の高さ、地震時の不便さ、洗濯物を外に干せないこと、大規模修繕の費用負担が大きい点が挙げられます。詳しくは「タワーマンションのデメリットは?」をご覧ください。









![東急不動産[ブランズ]BRANZ](/assets/images/original/high-rise-apartment-building-img-article-branz.png)