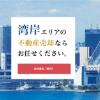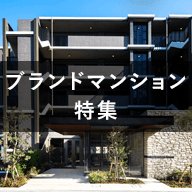タワーマンションは地震に強い?高層階の揺れと対策を解説

ざっくり要約!
-
タワーマンションの耐震性が高い理由は、建築基準や設備の安全性基準が厳しいこと、免震構造や制震構造が採用されていることです。
-
タワーマンションの高層階は長周期地震動の影響を受けやすく、大きな地震の際には揺れを強く感じる可能性があります。
-
エレベーターやライフラインが止まる事態に備え、1週間分の食料や飲料水、携帯トイレ、モバイルバッテリーなどを用意しておきましょう。
近年、日本では大規模の地震が頻発しています。2024年1月に発生した能登半島地震では、鉄筋コンクリート造のビルの損壊が見られました。
その後、8月の九州・日向灘の地震を受け、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が気象庁から発表されるなど、巨大地震への警戒が強まっています。タワーマンションにおける地震のリスクを不安視する方もいるでしょう。
この記事では、タワーマンションの耐震性や、想定されるリスクを解説します。地震後の生活に備える際のポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
タワマンの耐震性は総じて高い
はじめに結論をお伝えすると、タワーマンションの耐震性は総じて高いです。その理由には、主に以下の3つがあります。
- 超高層建築物の建築基準は厳格
- 設備の安全性基準も高い
- 「免震構造」や「制震構造」が採用されていることも
詳しく見ていきましょう。
超高層建築物の建築基準は厳格
タワーマンションの耐震性が高い理由のひとつは、超高層建築物に対する建築基準が厳格である点です。高さ60mを超える建築物は超高層建築物と呼ばれ、建築基準法によって厳しい耐震基準が適用されます。
具体的には、国土交通大臣の認定を受けるために、高度な構造計算や地震・強風時のシミュレーションが義務付けられており、震度6強~7程度の地震でも倒壊・崩壊しない設計となっています。
この厳格な基準により、タワーマンションは一般的な建物よりも高い耐震性を持つことが可能です。
設備の安全性基準も高い
タワーマンションの耐震性の高さは、構造だけでなく、設備の安全性基準の高さにも起因します。基準の一例を以下にまとめました。
| 規制内容 | 対象建築物の高さ | 法令 | 義務の有無 |
|---|---|---|---|
| 非常用エレベーターの設置 | 高さ31m超 | 建築基準法 第34条第2項 | 義務 |
| 緊急救助用スペースの設置 | 高さ31m超 | 消防法 消規第175号 | 指導(義務ではない) |
| 航空障害灯の設置 | 高さ60m以上 | 航空法第51条 | 義務 |
高さ31mを超える建築物には、建築基準法により非常用エレベーターの設置が義務付けられており、災害時の避難や救助活動を円滑に行うことが可能です。また、緊急救助用スペースの設置指導や、航空障害灯の設置の義務付けなどもあります。
これらの基準が、タワーマンションの安全性を高めることにつながっています。
「免震構造」や「制震構造」が採用されていることも
タワーマンションでは耐震性を高めるため、「免震構造」や「制震構造」が採用されているケースがあります。
免震構造は、建物と地盤の間に免震装置を設置することで、地震の揺れを吸収する仕組みです。一方、制震構造は、建物の構造体に制震装置(ダンパー)を設置し、地震の際の揺れを抑える構造です。
免震構造や制震構造の採用に法的義務はありませんが、タワーマンションの安全性を高める重要な要素となります。
タワーマンションの地震リスク

タワーマンションの耐震性は高いものの、やはりリスクはゼロではありません。想定される3つのリスクを見ていきましょう。
- 「耐震性が高い=揺れない」というわけではない
- 高層階は長周期地震動の被害を受けやすい
- エレベーターやライフラインが止まってしまうことも
それぞれ解説していきます。
「耐震性が高い=揺れない」というわけではない
耐震性が高いタワーマンションであっても、揺れを完全に防げるわけではありません。
耐震性とは、建物が地震に耐えられる強度を示す指標であり、建物が倒壊しにくいことを意味します。しかし、揺れ自体を防ぐことは難しく、高層階では特に揺れが増幅されやすくなります。
高層階は長周期地震動の被害を受けやすい
タワーマンションの高層階は、長周期地震動の影響を受けやすくなります。長周期地震動とは、周期が長く、ゆっくりとした大きな揺れが続く地震波のことです。主に大規模な地震の際に生じるものです。
周期とは揺れが1往復するのにかかる時間を指し、地震そのものの周期のほかに、建物にも固有の周期があります。高層建築物の固有周期は長いため、長周期地震動と共振し、上層階では揺れが増幅されるのです。
強い揺れが続くと、家具の転倒などのリスクがあります。家具・家電の固定や転倒防止器具の使用など、日頃から対策しておくことが重要です。
エレベーターやライフラインが止まってしまうことも
エレベーターは地震の際に自動的に停止し、弱い地震であれば自動復旧するシステムが搭載されている機種もあります。しかし、大きな地震が発生した際には再起動するために専門業者による点検が必要で、復旧までに時間がかかることが懸念されます。
また、電気や水道、ガスといったライフラインも地震の影響で停止することがあり、日常生活に支障をきたす可能性があります。
タワーマンションの「地震」に関する記事はこちら

タワーマンションは地震に強い?高層階の揺れと対策を解説
近年、日本では大規模の地震が頻発しています。2024年1月に発生した能登半島地震では、鉄筋コンクリート造のビルの損壊が見られました。8月の九州・日向灘の地震を受け、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されるなど、巨大地震への警戒が強まっており、タワーマンションにおける地震のリスクを不安視する方もいるでしょう。 本記事では、タワーマンションの耐震性や、想定されるリスクを解説します。
「地震 マンション」に関する記事はこちら

地震発生時のマンションの倒壊リスクは?地震のトイレ問題や住宅ローンも解説
地震発生時のマンションの倒壊リスクは?地震のトイレ問題や住宅ローンも解説 のページ。「いつでもあなたの傍に置いていただける身近な存在であり続けたい」そんな願いをこめて東急リバブルが提供する不動産メディアです。
地震の「後」に備えることも大切
タワーマンションでは、地震が発生した際に在宅避難を求められたり、電気が復旧するまでは生活しづらかったりします。
ここでは、地震後の生活に備える際のポイントを見ていきましょう。
マンションの住人は基本的に「在宅避難」を求められる
タワーマンションの住人は、地震後には基本的に在宅避難を求められます。マンションの耐震性が高く、建物自体の倒壊リスクが低いためです。避難所の収容人数には限りがあるため、自宅で安全に過ごせる人は在宅避難が推奨されています。
また、避難所ではプライバシーの確保が難しく、ストレスから体調を崩す恐れもあります。住み慣れたマンションで生活を続けられることも、在宅避難が推奨される理由のひとつです。
電気が復旧するまで生活しづらい
タワーマンションでは、停電するとエレベーターやトイレが使用できなくなり、電気が復旧するまでは生活しづらくなることが予想されます。エレベーターが停止すると、高層階の住人は階段での移動を強いられ、外出や物資の運搬が大変になるでしょう。
また、マンションの給排水ポンプを動かす際にも電気が必要です。給水ポンプは高層階へ水を運ぶもので、排水ポンプは汚水や雑排水を下水管に流すためのポンプです。いずれも電気で作動するため、たとえ水道が止まっていなくても、停電すると水まわりが使用できなくなります。
自分でできる備えをしておく
タワーマンションでは管理組合が災害備蓄を行っていることもありますが、住人も自分で備えておくことが大切です。
たとえば非常食や飲料水、常備薬などの備蓄のほか、携帯トイレなどを用意しておきます。大規模な地震の際には、電気や水道の復旧に時間がかかるため、一週間分を備えておくと安心です。
また、携帯ラジオやモバイルバッテリー、懐中電灯なども必須アイテムです。非常時の連絡手段や避難経路の確認もしておきましょう。
まとめ
タワーマンションは、一般的な建築物よりも耐震性が高くなっています。その理由として、超高層建築物には厳しい建築基準や設備の安全性基準が設けられていることが挙げられます。
しかし、高層階では長周期地震動の影響を受けやすく、強い揺れを感じることもあるでしょう。また、エレベーターやライフラインが止まる恐れもあるため、地震後の生活に備えておくことが大切です。
耐震性の高いタワーマンションをお探しの際は、ぜひご相談ください。東急リバブルでは、さまざまな条件にあわせた物件のご提案が可能です。
ワンポイントアドバイス
地震発生後、ライフラインが止まってしまうと、タワーマンションでは日常生活に大きな支障をきたします。日頃から、停電時の生活をシミュレーションし、食料や必要な物資を準備しておきましょう。
そのほか、定期的に防災訓練に参加したり、居住者間でコミュニケーションを取ったりすることも、緊急時の対応力を高める上で大切です。備えを充実させることで、災害時の不安を軽減し、より安全に過ごすことができるでしょう。
Q. タワマンの耐震性は高いですか?
A.タワーマンションの耐震性は総じて高いです。超高層建築物の建築基準は厳格で、設備の安全性基準も高くなっています。また、「免震構造」や「制震構造」が採用されていることも。その理由には、主に以下の3つがあります。詳しくは「タワマンの耐震性は総じて高い」をご覧ください。
Q. タワマンの地震リスクはどのくらいですか?
A. タワーマンションの耐震性は高いものの、やはりリスクはゼロではありません。詳しくは「タワーマンションの地震リスク」をご覧ください。
Q.地震後、タワマンに住んでいたら何に備えるべきですか?
A. タワーマンションでは、地震が発生した際に在宅避難を求められたり、電気が復旧するまでは生活しづらかったりします。詳しくは「地震の「後」に備えることも大切」をご覧ください。








![東急不動産[ブランズ]BRANZ](/assets/images/original/high-rise-apartment-building-img-article-branz.png)