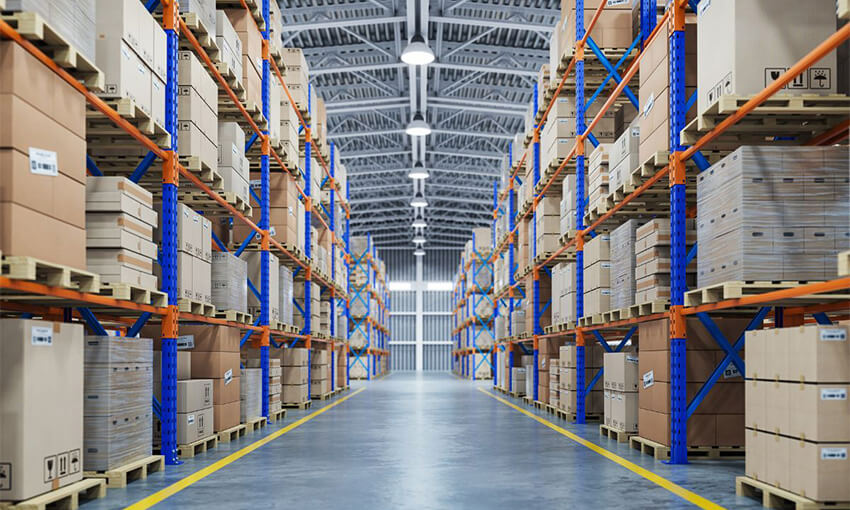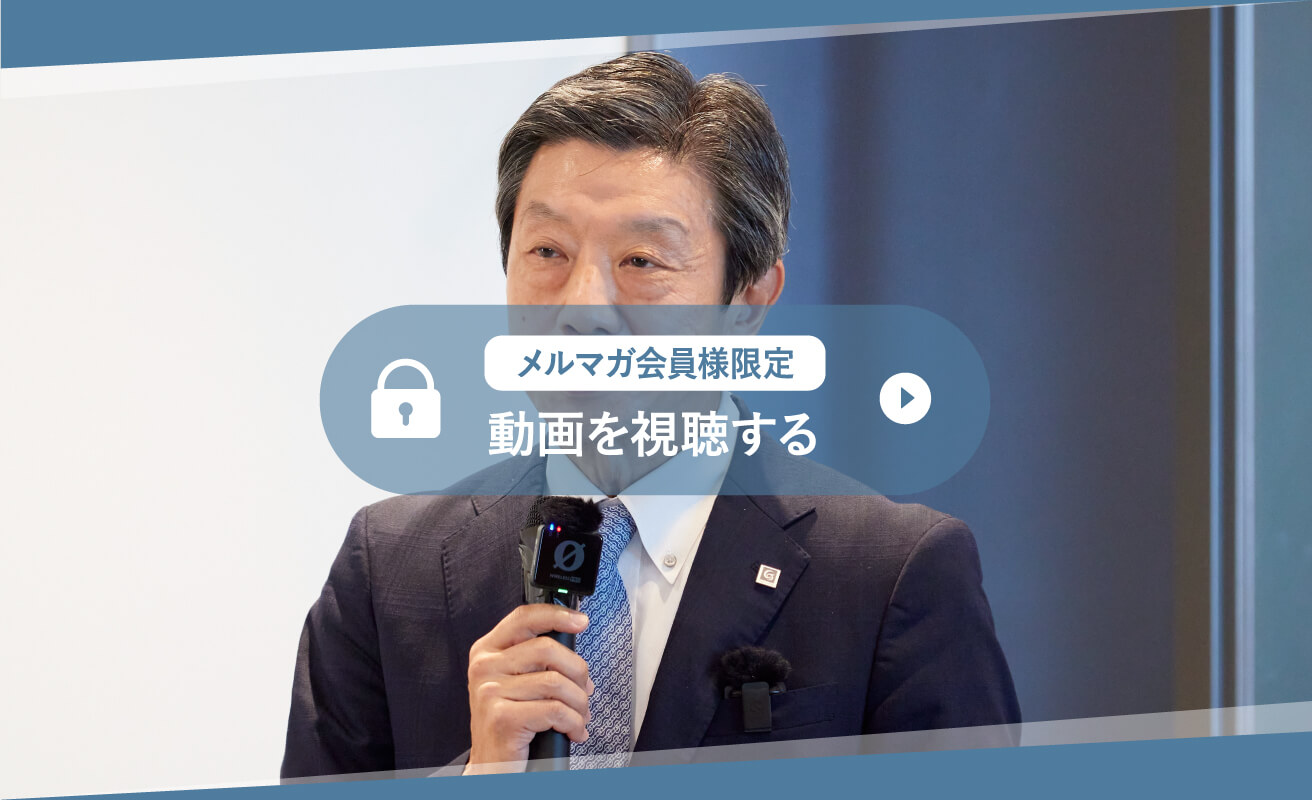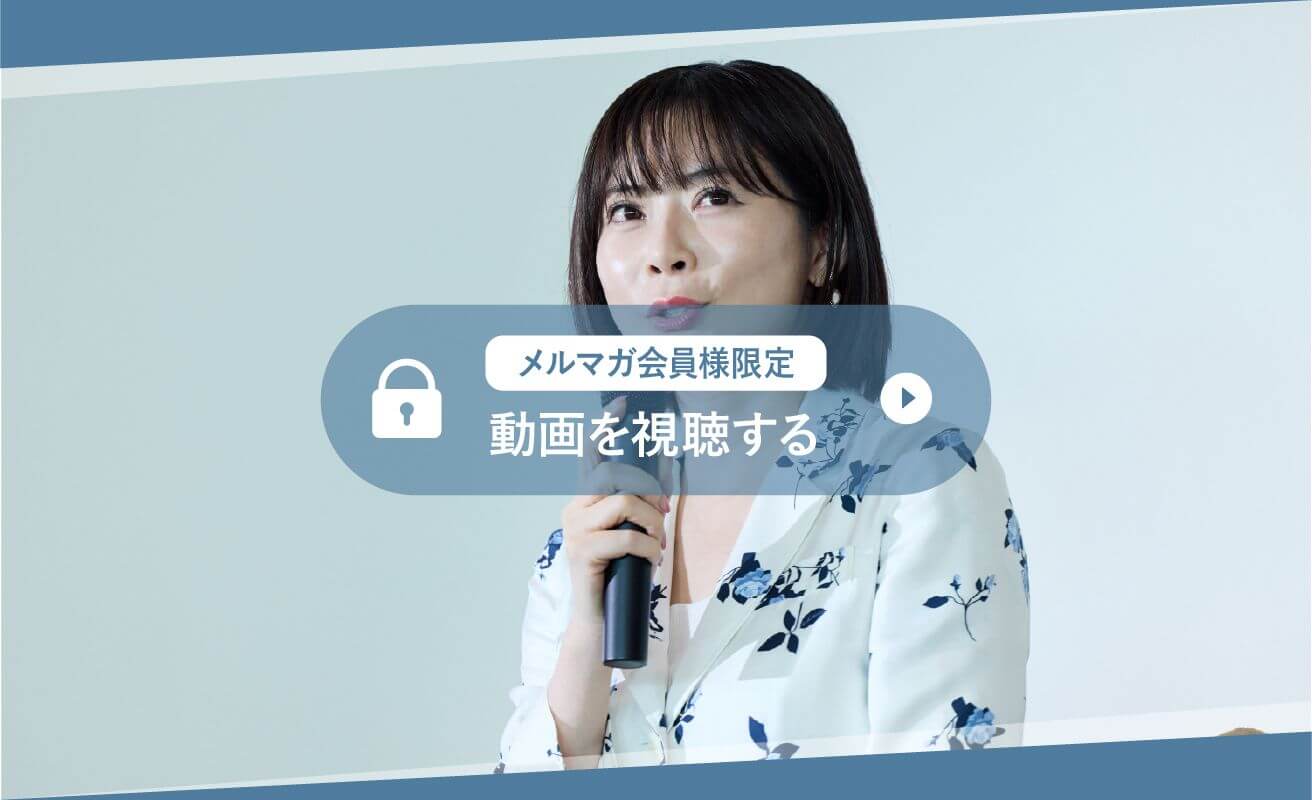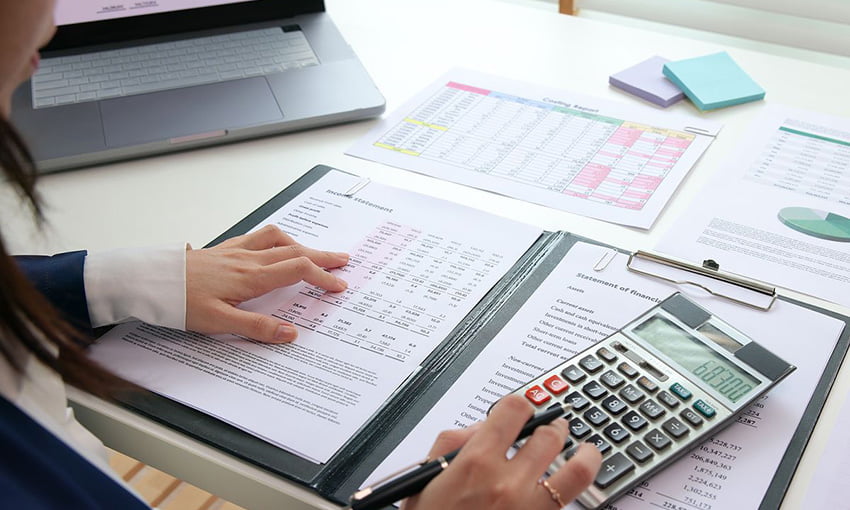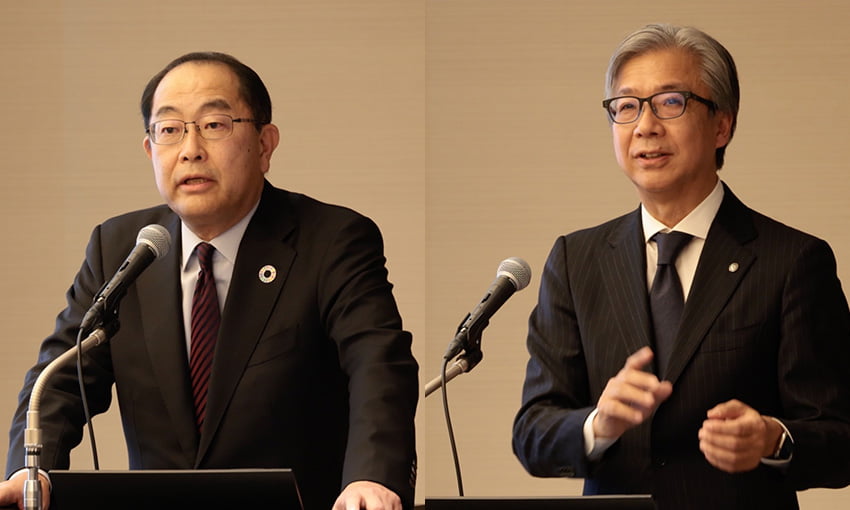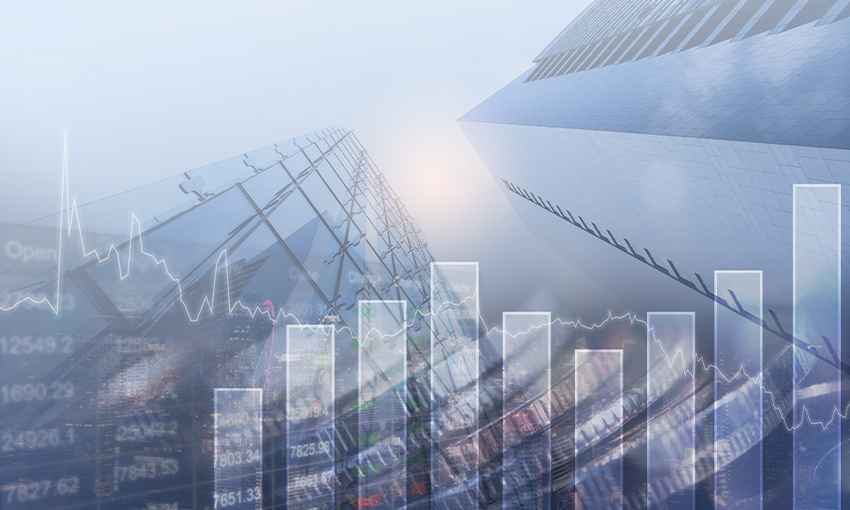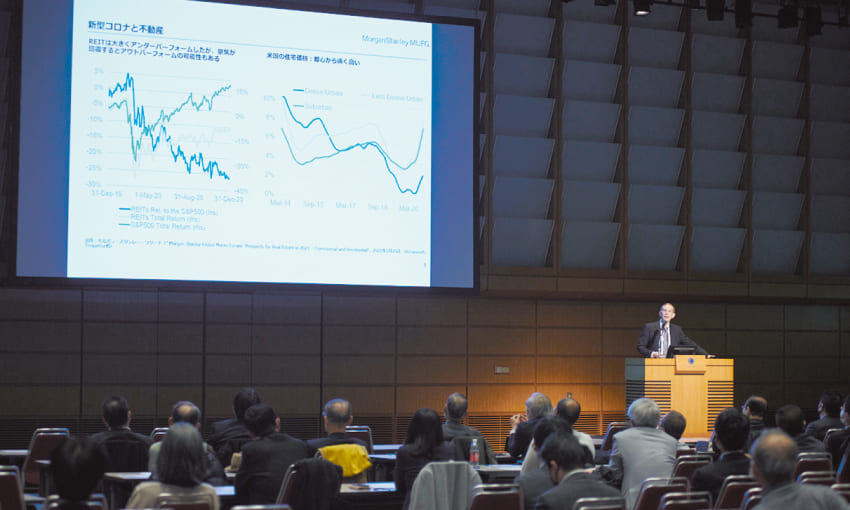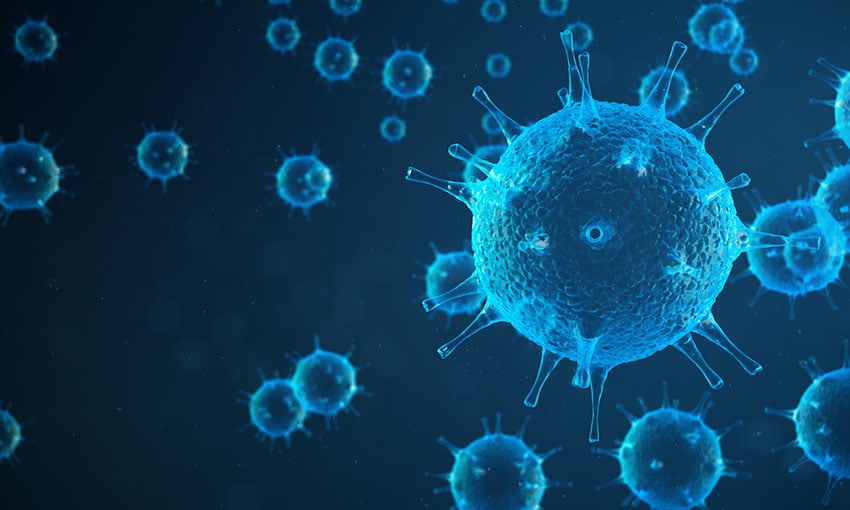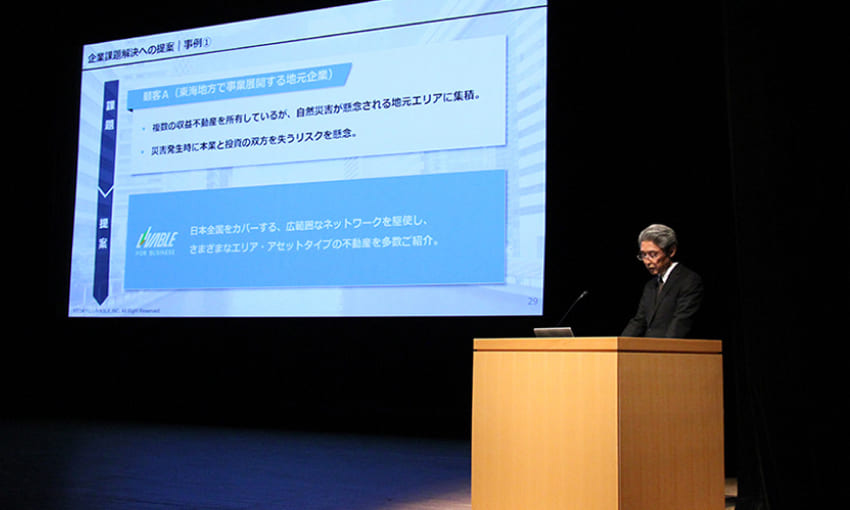キャッシュフローとは?計算方法から改善の仕方、企業不動産の経営戦略まで解説
#有効活用
#事業用不動産
#老朽化・遊休資産
#税金・コスト

企業の成長と安定を支える「キャッシュフロー」は、経営で最も重要な指標のひとつです。売上は上がっているのに会社が倒産してしまう「黒字倒産」が起こるのは、実際の現金の流れがうまく管理できていないからです。
会社が保有する不動産が、キャッシュフローに大きな影響を与えることをご存知でしょうか。不動産は会社の資産の大部分を占めているケースが多いため、その取得・維持・運用・売却の各段階で現金の流れに直接影響します。
この記事では、キャッシュフローの基本や、経営における重要性、さらに保有不動産を活用した具体的な改善方法を詳しく解説します。キャッシュフロー計算書の読み方から実践的なCRE戦略まで、経営に役立つ情報を紹介するためぜひご覧ください。
資産価値を最大化するための不動産戦略をサポート
売却・査定について
目次
1. キャッシュフローとは?

キャッシュフローとは、企業における一定期間の現金などの増減を示すもので、損益計算書や貸借対照表では見えにくい「お金の流れ」を可視化する重要な指標です。
なぜキャッシュフローが重要なのでしょうか。その理由は、企業では売上が計上されても、すぐに現金が入ってくるとは限らないからです。商品が売れても売掛金として記録されるだけで、実際の入金は数ヶ月後というケースは珍しくありません。このような帳簿上の売上と手元の現金のずれを把握するために、キャッシュフローの概念が不可欠なのです。
キャッシュフローは企業の存続と成長にとって「生命線」です。 その重要性は主に3つの観点から理解できます。
まず、「黒字倒産」を防ぐためです。利益が出ていても手元に現金がなければ、仕入れ代金や従業員の給与、家賃などの支払いができません。大きな利益が出ていても現金が枯渇すれば企業は倒産してしまいます。
次に、金融機関や投資家からの信用を高めるためです。安定したキャッシュフローは、企業が負債を滞りなく返済できる能力や将来の成長投資の余力があることを示します。これにより新たな融資や投資を受けやすくなり、資金調達の選択肢が広がります。
最後に、経営者の意思決定の精度を向上させることが挙げられます。キャッシュフローを正確に把握することで、「設備投資の実行可能性」「新規出店の最適時期」「不採算事業からの撤退判断」などの重要な経営判断を、資金の裏付けをもって行えます。
まとめると、キャッシュフローの正しい理解は、企業の戦略的成長には欠かすことができません。
2. キャッシュフロー計算書の見方と作り方

キャッシュフローの状況は、キャッシュフロー計算書で確認できます。この計算書では、企業のお金がどのように増減したかを「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つに分けて整理します。
キャッシュフローの種類ごとの違いは以下の通りです。

3つに分かれている理由は、それぞれ異なる企業活動を表しており、プラスが望ましいものもあれば、マイナスでも将来への投資として評価されるものもあるからです。以下でそれぞれ解説します。
1.営業活動によるキャッシュフロー
企業の本業による現金の増減を示します。具体的には、商品の販売による収入、仕入れ・人件費・家賃などの支払いといった日常的な事業活動から生じるキャッシュの流れです。不動産事業では、賃料収入、管理委託費、修繕費の支払いなどがここに計上されます。
営業キャッシュフローがプラスであることは、本業が順調に現金を創出していることを意味し、企業の安定性を測る最も重要な指標です。
2.投資活動によるキャッシュフロー
固定資産の取得・売却、株式投資や有価証券の売買など、企業の投資活動に伴う現金の増減を示します。具体的には、設備投資、有価証券の取得・売却、貸付金の回収などが含まれます。不動産関連では、投資用不動産の購入費用、新規開発用地の取得費用、大規模リノベーション費用はマイナス要因、保有不動産の売却収入はプラス要因となります。
投資キャッシュフローは企業の将来への投資姿勢を表しており、成長のための先行投資でマイナスになることが多い傾向にあります。
3.財務活動によるキャッシュフロー
資金調達や返済に関する現金の増減を示します。具体的には、借入金や社債の発行・返済、株式の発行、配当金の支払いなどが含まれます。不動産関連では、不動産担保融資の新規借入はプラス、その返済はマイナスに計上されます。
財務キャッシュフローは企業の資金調達戦略を反映しており、借入でプラス、返済や配当でマイナスという基本構造で外部からの資金調達と返済のバランスを示す重要な指標です。
これらの3つのキャッシュフローを理解することで、会社がどこで現金を稼ぎ、どこに使い、どのように資金を調達しているのかを把握できます。
2.1. キャッシュフローの具体例
不動産を賃貸している会社を例に、具体的な数値でキャッシュフローの内訳を見てみましょう。
【前提条件】
- 年間家賃収入:1,200万円
- 年間運営経費:200万円(管理費、修繕費、固定資産税など)
- 物件購入費用:8,000万円
- 借入金:6,000万円
- 借入金の年間返済額:300万円(うち元本200万円、利息100万円)
- 減価償却費:150万円(非現金支出)
- 新規物件の購入:2,000万円
- 物件の売却収入:1,000万円
- 新たな借入金:500万円
- 配当金の支払い:100万円
1. 営業活動によるキャッシュフロー
本業である不動産賃貸事業から生み出された現金を示します。
計算式:営業活動によるキャッシュフロー = (家賃収入 - 運営経費) - (元本を除くローン利息) + 減価償却費
- 数値例:
(1,200万円 - 200万円) - 100万円 + 150万円 = + 1,050万円
このプラスの数値は、本業が順調に現金を稼ぎ出していることを意味します。この現金が多ければ多いほど、会社は安定していると評価できます。
2. 投資活動によるキャッシュフロー
将来の成長のために、設備や資産にどれだけお金を投じたかを示します。
計算式:投資活動によるキャッシュフロー = 物件の売却収入 - 新規物件の購入費用
- 数値例:
1,000万円 - 2,000万円 = - 1,000万円
このマイナスの数値は、積極的に将来の成長に投資していることを示しています。新規物件の取得など、事業拡大のための支出が売却収入を上回っているためです。成長期にある企業では、このキャッシュフローがマイナスになることが多い傾向にあります。
3. 財務活動によるキャッシュフロー
会社の資金調達や返済の状況を示します。
計算式:財務活動によるキャッシュフロー = 新たな借入金 - 借入金の返済元本 - 配当金の支払い
- 数値例:
500万円 - 200万円 - 100万円 = + 200万円
このプラスの数値は、借入金などによる資金調達が、返済額や配当金の支払いを上回っていることを示しています。これは、事業拡大に必要な資金を外部から調達している状況を反映していると解釈できます。
まとめると、本業で稼いだ現金と借入金を合わせて、積極的に事業拡大(物件購入)を進めているという企業の姿勢が見て取れます。このように3つのキャッシュフローを組み合わせることで、会社の「お金の流れ」の全体像を深く理解することができます。
なお、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローから算出される「フリーキャッシュフロー」は、企業経営における最重要指標のひとつです。
フリーキャッシュフローは、営業活動で生み出した現金から設備投資などの必要な支出を差し引いたあとに残る、企業が真に「自由に使えるお金」を表します(フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー + 投資キャッシュフロー)。
この数値がプラスの企業は、借金返済、配当、買収、新規事業投資など多様な選択肢を持ち、企業価値向上の施策を実行できます。
マイナスの場合、事業収益だけで投資をまかなえておらず、財務戦略の見直しが必要な危険信号です。ただし、一時的な赤字企業でも資産売却で手元資金が増えることもあるため、損益とキャッシュフロー両面での評価が重要です。
実際にフリーキャッシュフローを分析する際は、単年度の数値だけでなく、数年間のトレンドを把握することが不可欠です。フリーキャッシュフローを評価する場合、一年だけでなく数年間の数字の変化を見て、継続して現金を生み出せているか、右肩上がりで伸びているかを確認し、変動がみられるときはその要因を分析することが重要です。
2.2. キャッシュフロー計算書の作り方
ここまでで、キャッシュフロー計算書が企業の現状を把握する上でいかに重要であるかをお伝えしました。では、この重要な計算書は、具体的にどのような方法で作られているのでしょうか?
キャッシュフロー計算書の作成方法には、「直接法」と「間接法」の2種類があります。
直接法は、入出金を項目ごとに直接記載していく方法です。営業活動であれば顧客からの入金、社員への給与支払い、仕入先への支払いなどをひとつひとつ積み上げて計算します。直感的にわかりやすく、資金の動きが明確に把握できるという特徴があります。IFRS(国際会計基準)で推奨される方法ですが、個々の取引を細かく記録する必要があるため手間がかかります。
間接法は、損益計算書上の税金等調整前当期純利益からスタートし、そこから現金の動きを伴わない項目(例えば減価償却費など)を調整することで、営業活動によるキャッシュフローを算出する方法です。多くの企業で採用されており、作成が比較的容易という特徴があります。利益と資金の関係把握に有効なため、日本企業で広く採用されています。
手順1:損益計算書より税金等調整前当期純利益を確認
間接法では、この利益を出発点として、現金の増減に影響を与えない会計上の項目をひとつずつ調整していきます。
手順2:非資金損益項目の調整
損益計算書上は費用や収益として計上されていても、実際には現金の動きを伴わない項目を調整します。代表例が減価償却費の加算です。減価償却費は、建物や設備などの固定資産の取得費用を耐用年数にわたって費用配分する会計処理ですが、実際に現金が減少する支出ではありません。そのため、税金等調整前当期純利益に加算する必要があります。
手順3:営業活動に伴う債権・債務の増減を調整
売掛金、買掛金、未収入金、未払金など、営業活動に伴う債権・債務の増減を調整し、実際の現金収支に合わせます。売掛金が増加すれば(売上が増えたがまだ入金されていない状況)、利益は増えても手元の現金は増えていないため、営業キャッシュフローは減少します。逆に買掛金が増加すれば(仕入れしたがまだ支払っていない状況)、手元の現金は減っていないため、営業キャッシュフローは増加します。
不動産関連事業の担当者は、自社の不動産事業や保有不動産に関連する具体的な取引が、3つのキャッシュフローのどの項目に計上されるのかを理解することが重要です。
直接法を採用している場合、営業活動によるキャッシュフローでは、賃貸物件からの賃料収入、不動産管理受託によるフィー収入、駐車場の使用料などの収入項目と、不動産の修繕費、管理委託費、水道光熱費、固定資産税、火災保険料などの支出項目を把握します。実際の現金の動きが直接確認できるため、資金繰りの把握や資金計画の立案が容易になります。
間接法を採用している場合、営業活動によるキャッシュフローでは、税金等調整前当期純利益からスタートし、現金の動きを伴わない減価償却費やのれん償却費などを加算します。
とくに注意すべきは債権・債務の変動です。未収の賃料が増えれば営業キャッシュフローは減少し、敷金・保証金の受領や返還、大規模修繕の未払金増加なども営業キャッシュフローに影響します。そのため、テナントの入居・退去や修繕のタイミング把握が重要です。間接法では、会計上の利益と実際の現金がなぜ異なるのかを理解できるため、財務分析に優れています。
どちらの方法でも、投資キャッシュフローでは、保有不動産の売却収入などの収入項目と、新たな投資用不動産の購入費用、既存物件の大規模リノベーション費用などの支出項目を管理します。
3. 企業経営におけるキャッシュフロー戦略

キャッシュフロー計算書を作成し分析することで、企業経営において以下のような効果が期待できます。
より戦略的な資金繰りが可能となる
自社のキャッシュフローパターンを分析することで、将来の資金ショートリスクを予測し、早期に対策を講じることができます。
例えば、営業キャッシュフローは毎年安定して5億円のプラスだが、投資キャッシュフローが新規物件取得年にはマイナス10億円、通常年にはマイナス1億円と変動が大きい企業の場合を考えてみましょう。このパターンを把握していれば、大型投資の前年から段階的な資金調達や営業キャッシュフローの蓄積を計画することで、資金ショートを回避できます。
また、賃料収入の安定性や修繕費・管理費などの支出トレンドを把握することで、より精度の高い資金繰り予測が可能になります。 例えば、月額賃料収入が安定して1,000万円あり、年間修繕費が平均200万円の場合、不動産事業による営業キャッシュフローへの貢献度を年間1億円程度と見込んで資金計画を立てることができます。
このような分析により、特定の時期に大きな設備投資を予定している場合でも、事前に資金調達の準備や営業活動からのキャッシュ創出強化などの対策を講じることができます。
フリーキャッシュフローから戦略的なリソース配分が見えてくる
フリーキャッシュフローは、企業が成長のために使える余剰資金です。これが豊富であれば、新規事業への投資、M&A、研究開発、株主還元など、さまざまな成長戦略にリソースを配分できます。
逆に不足している場合は、事業の効率化やコスト削減、資産売却など、抜本的な対策が必要という危険信号となります。
事業投資の採算性チェックに役立てることが可能
新規事業や設備投資の計画を立てる際、投資キャッシュフローと将来の営業キャッシュフローの関連性を分析することで、その投資がどれだけキャッシュを生み出し、採算が取れるかを評価できます。
例えば、新たな物流倉庫の建設を計画する場合、建設費用(投資キャッシュフロー)と、その倉庫が生み出す賃料収入や効率化によるコスト削減効果(営業キャッシュフロー改善)を比較し、プロジェクトの妥当性を評価します。投資対効果をキャッシュフローの観点から検証することで、よりリスクの少ない効果的な投資判断を下せるようになります。
これらの分析を通じて、経営者は自社の「稼ぐ力」を理解し、未来に向けた具体的な行動計画を策定できるようになります。
4. キャッシュフロー改善とCRE戦略

キャッシュフローの改善は、企業価値向上に直結する経営課題です。とくに、企業が保有する不動産の最適化は、キャッシュフローの改善に大きく貢献し、結果として企業価値を最大化させる強力な手段となります。
不動産は、企業にとって多額の投資を伴い、維持管理にもコストがかかる一方、収益を生み出す源泉にもなり得ます。そのため、CRE戦略を適切に実行すれば、3つのキャッシュフローのすべてに好影響を与え、キャッシュフロー全体の健全化が期待できます。
まずは一般的なキャッシュフロー改善のポイントをいくつかご紹介します。
1.売掛金のチェック
売掛金の回収サイト(入金までの期間)を短期化する交渉を行ったり、取引先の与信チェックを強化して貸し倒れリスクを低減したりすることで、手元資金の早期確保につながります。
2.取引ごとの粗利チェック
個々の取引の粗利率を定期的に見直し、収益性の低い取引を改善したり、ボリュームディスカウントの適用余地などを確認したりすることで、売上高に対する現金の確保率を高めます。
3.売上債権の売却(ファクタリング)
売掛金を金融機関や専門業者に売却することで、期日前の現金化が可能です。緊急の資金ニーズがある場合に有効な手段です。
4.資金調達方法の見直し
低金利の融資への借り換え、補助金や給付金の積極的な活用、クラウドファンディングなど、多様な資金調達方法を検討することで、資金調達コストを抑え、キャッシュアウトを抑制できます。
5.不要な保有資産の処分
使用していない機械設備など、事業に貢献しない遊休資産を売却することで、売却益を得てキャッシュを創出し、固定費も削減できます。
上記のなかでも、「不要な保有資産の処分」に代表されるように、CRE戦略はキャッシュフロー改善に直接的に貢献できる非常に有効な手段です。不動産は企業の固定資産のなかでも大きな割合を占めるため、その運用改善はキャッシュフローに大きなインパクトを与えます。
関連記事:CRE戦略とは?不動産で企業価値を高める中長期的な戦略を詳しく解説
4.1. キャッシュフローを改善する施策と成功事例
これらを踏まえた、CRE戦略を通じて実践できるキャッシュフローの改善施策は以下のとおりです。
1.遊休不動産の処分
未使用の土地や建物、事業性が低下した遊休不動産を売却することで、売却益による投資キャッシュフローのプラスと継続的コスト削減による営業キャッシュフローの改善という二重の効果が期待できます。保有不動産の棚卸しにより、遊休化している物件がないかチェックすることが重要です。
遊休不動産の処分は売却益によるキャッシュ取得とコスト削減の両方が期待できる一方で、将来的な含み益の機会損失や簿価割れによる損失、売却にかかる手間など、デメリットが存在することも押さえておきましょう。
例えば、製造メーカーA社は、遠方に所有する遊休地の維持管理コストに悩んでいました。道路拡幅により狭小地となってしまったため、「売却が長期化するのでは」との懸念から、長年取引のある大手信託銀行への相談も躊躇している状況でした。
そこで、不動産会社は狭小地であっても用途次第で十分な購入需要があることをA社に説明し、アパート・店舗・駐車場の3つの用途に絞って資産価値を算出し、最も価値の高い用途での買手探索を行った結果、期限内にA社の希望条件を上回る価格での売却を実現しました。
物件特性を正確に把握した戦略的なアプローチと機動力により、売主の不安を解消できた事例です。
関連記事:遊休地など十数物件を期日内に売却。希望条件に応じた売却手法で利益最大化を実現
関連記事:資産効率向上のための、年度内の資産売却
2.リースバックの活用
自社が所有する不動産を売却し、同時にその不動産で賃貸借契約を結んで継続して使用する手法です。売却によりまとまった現金を得られるため、売却益として投資キャッシュフローがプラスとなり、運転資金の確保や新規事業への投資などに充てることができます。不動産は手放したいが事業拠点としては利用したい、という場合に非常に有効です。
他方、リースバックは家賃という固定費の増加が認められるほか、締結する賃貸借契約の内容によっては、改装・増床・解約などの自由度が下がる可能性があります。
そういった意味でも、リースバック契約は、個人・法人を問わず、契約内容を十分に確認することが不可欠です。賃料の改定条件や契約期間、再購入(買戻し)の可否など、不利な条項が含まれていないか、専門家を交えて慎重に確認することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
関連記事:セールアンドリースバックとは?実施目的や具体例、会計処理のポイント
3.本社や事業所の再編
現在の本社や事業所が、企業の規模や事業内容に対して過剰なスペースであったり、賃料が高い立地であったりする場合、より効率的でコストの低いオフィスや事業所への移転・集約を検討します。これにより、賃料などの固定費を大幅に削減でき、営業キャッシュフローの改善につながります。また、既存の所有不動産を売却することで、多額の現金を得ることも可能です。
ただし、事業所や本社機能の再編には一時的なコストがかかります。また、社員への丁寧な説明がないとモチベーションや生産性の低下にもつながりかねません。トップダウンで移転を決定するのではなく、社員の声も可能な限り反映させた再編が望ましいでしょう。
例えば、ある大手家電メーカーは、販売チャネルの変化と生産拠点の海外移転により、棚卸資産の増加と物流コストの上昇に直面し、キャッシュフローの悪化が課題となっていました。
そこで、全国20ヵ所に分散していた物流拠点を3ヵ所(本州2ヵ所、北海道1ヵ所)に集約する施策を実施したことで、各拠点での安全在庫が不要となり、棚卸在庫を32%圧縮することに成功し、キャッシュフローを改善しました。
また、集約と同時に、輸送モードの変更やコンテナ直送などを導入することで、物流コストを9%削減し、利益率も向上させました。この施策では、配送先のサービスレベル調整や、社内調整といった新たな課題も発生しましたが、顧客や関係部署との連携によって解決し、大幅なバランスシートの縮小と投下資本利益率の上昇を実現しました。
4.所有不動産の証券化(オフバランス化)
保有する不動産を特別目的会社(SPC)などに売却し、その不動産から得られる収益を元にした証券を発行して投資家から資金を募る手法です。これにより、不動産が企業の貸借対照表から切り離され(オフバランス化)、負債勘定を圧縮できます。資金調達の多様化にもつながり、財務キャッシュフローの改善に貢献します。
所有不動産の証券化は、財務体質の改善に役立つ一方で、デメリットも伴います。まず、所有権が手元からなくなるため、利用の自由度が下がる点が挙げられます。また、SPC設立や専門家への報酬といった多額の初期費用がかかり、運営も複雑化する傾向にあります。
これらのデメリットを避けるには、専門家へ相談し、費用対効果を事前に綿密に分析することが不可欠です。また、契約内容をよく精査し、将来的な運営方針への制約を最小限に抑えるための条項を盛り込むことが重要です。
関連記事:オフバランスとは?手法やメリットについてわかりやすく解説
5.賃貸借条件の見直し
企業が不動産を貸している場合は、賃料アップ交渉や、契約期間の見直し、保証金・敷金の増額などを検討し、賃料収入などの営業キャッシュフローを向上させます。借りている場合は、賃料の値下げ交渉や、敷金・保証金の減額要請、フリーレント期間の交渉などを行い、賃料支出などの営業キャッシュフローを改善します。
賃貸借条件の見直しはキャッシュフロー改善に有効ですが、貸主・借主双方にデメリットがあります。貸主が賃料アップを求めると、借主が退去してしまうリスクがあり、空室期間が生じます。一方、借主が値下げ交渉を行うと、貸主との関係が悪化し、契約更新時に不利な条件を提示されることも想定されます。
これらのリスクを避けるには、交渉前に周辺相場や物件の価値を客観的に把握し、双方にとって納得できる妥協点を探ることが重要です。また、日頃から良好な関係を築いておくことも有効な回避策となります。
6.バリューアップ施策
既存物件でリノベーションやコンバージョン(オフィスビルをマンションに、倉庫をオフィスに改修するなど建物の用途変更をすること)を行うことで、物件の収益力を向上させることができます。例えば、老朽化したオフィスビルをシェアオフィスや商業施設に改修することで、より高額な賃料設定や稼働率向上が可能です。一時的に改修費用として投資キャッシュフローマイナスは発生しますが、長期的に見ればキャッシュフローを最大化させることができます。
関連記事:老朽化とバリューアップ|企業に求められる不動産戦略のポイント
これらのCRE施策は、単発的な効果に留まらず、営業・投資・財務の各キャッシュフローに対して相互連関的な効果をもたらす点が特徴です。例えば、リースバックは投資キャッシュフローでの資金創出と同時に営業キャッシュフローでの賃料負担を生み、証券化は投資キャッシュフローと財務キャッシュフローの両方に影響を与えます。
重要なのは、財務部門と連携し、どのような施策を講じると、どのようにキャッシュフローへ影響を与えるかを正確に把握しながらCRE戦略を立案し実行することです。従来の「不動産管理」から「キャッシュフロー改善・最大化のパートナー」への役割転換により、CRE戦略は財務戦略と一体となった経営戦略の中核を担う存在となるでしょう。
5. キャッシュフローを理解して、的確な経営戦略を実行しよう

キャッシュフローは、企業経営の「生命線」です。帳簿上は黒字でも、手元にお金がなければ会社は倒産してしまいます。営業・投資・財務の3つのキャッシュフローを分析することで、会社の本当の財務状況と将来性がわかります。
企業が保有する不動産は、キャッシュフロー改善に大きく貢献できます。使わない不動産の売却、リースバックの活用、賃料の見直し、物件の価値向上など、さまざまな方法でお金の流れを改善することができます。
この機会に自社の不動産がお金の流れにどう影響するかを理解し、戦略的な不動産活用で会社の成長を支えていきましょう。
関連記事:事業用不動産の売却|手順や方法、費用・税金、ポイントなどを解説
宅地建物取引士
佐藤 賢一 氏
Kenichi Sato
大学卒業後、不動産業界一筋。賃貸仲介・管理から売買仲介まで幅広い実務を経験した後、専門性を深め、プライム企業にて信託関連のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務に従事。
現在は注文住宅会社の不動産部門責任者を務めつつ、多様な経験を活かし兼業ライターとしても活動中。不動産の実務から投資・管理戦略まで、多角的な視点に立ったわかりやすい解説を得意としています。
※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。