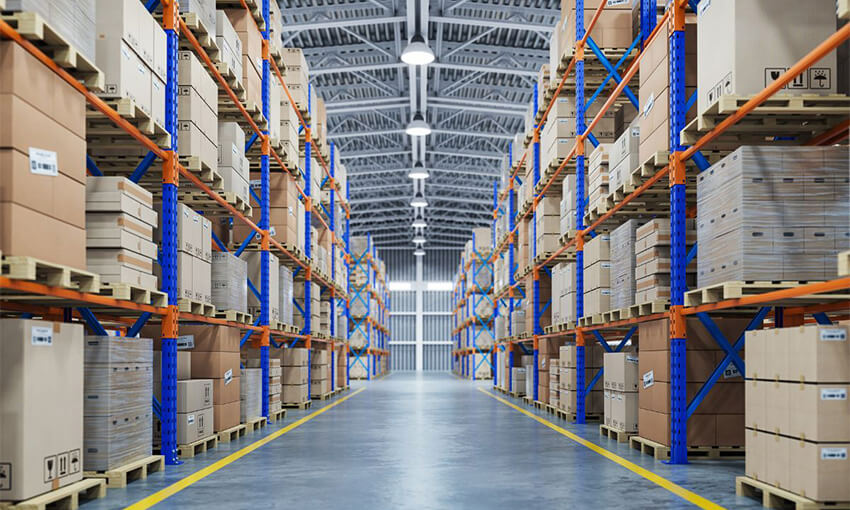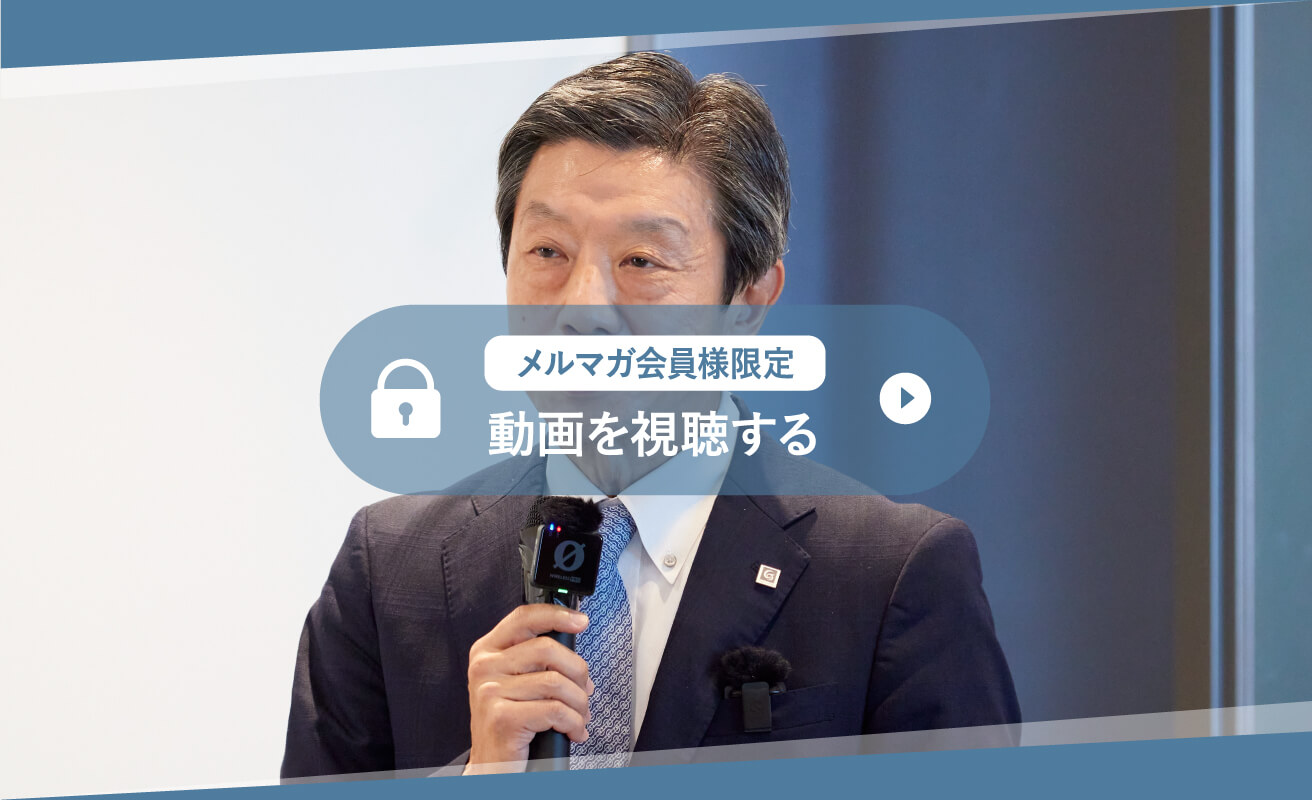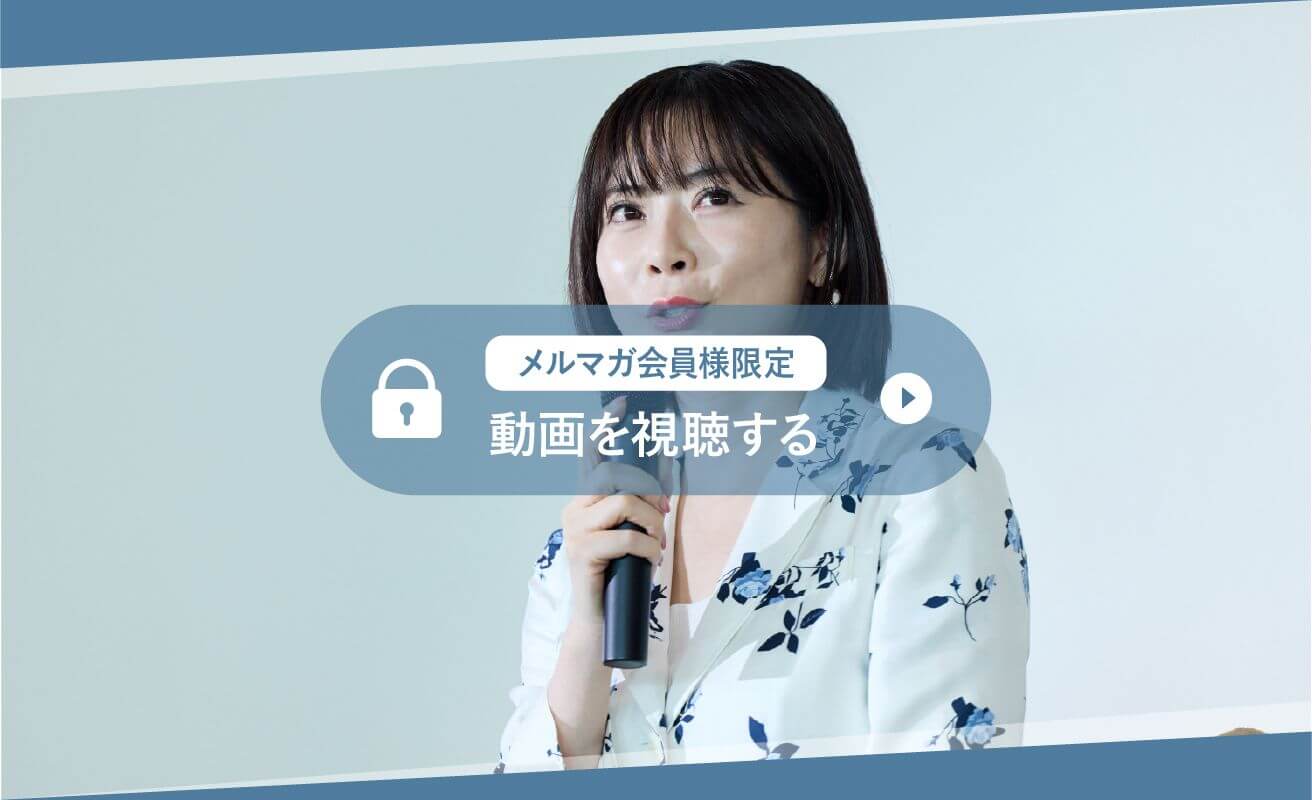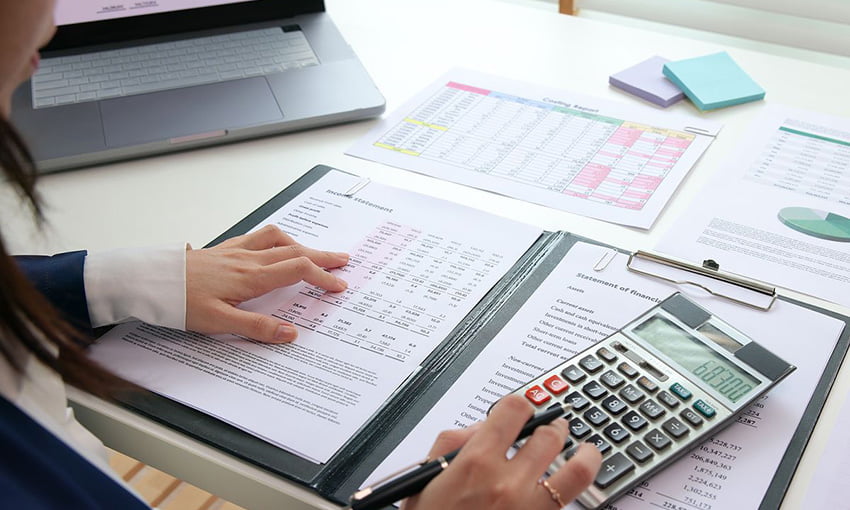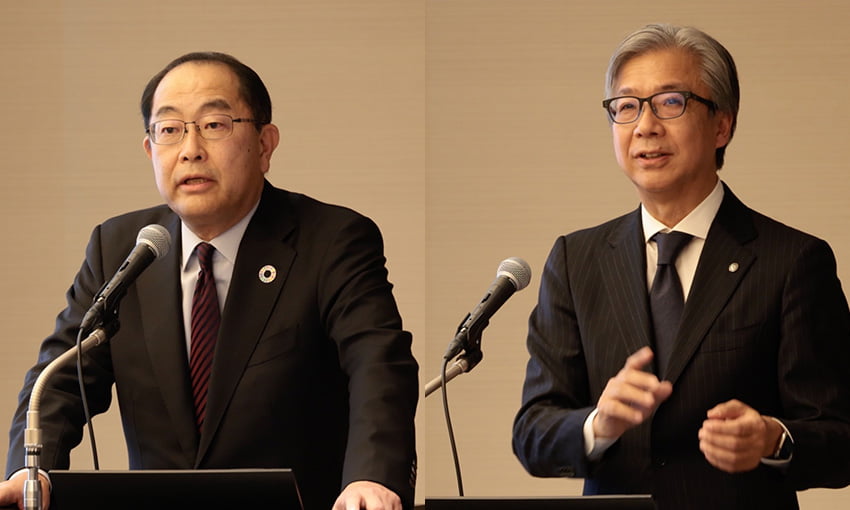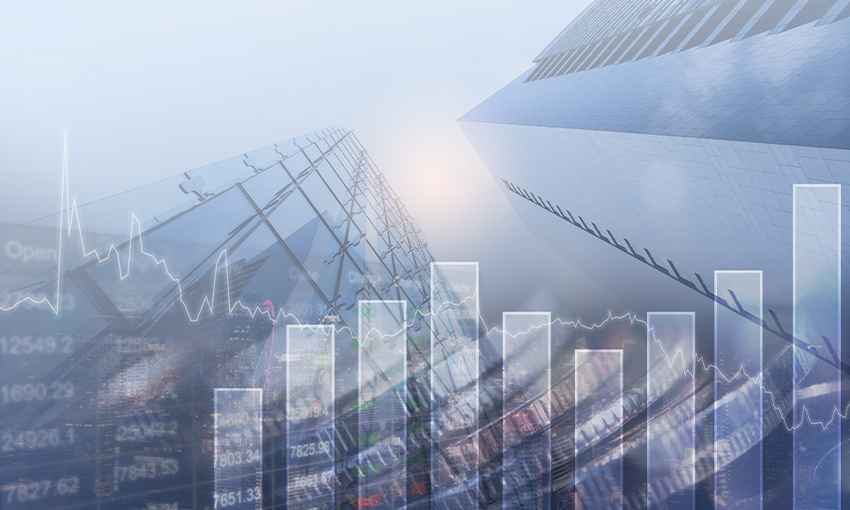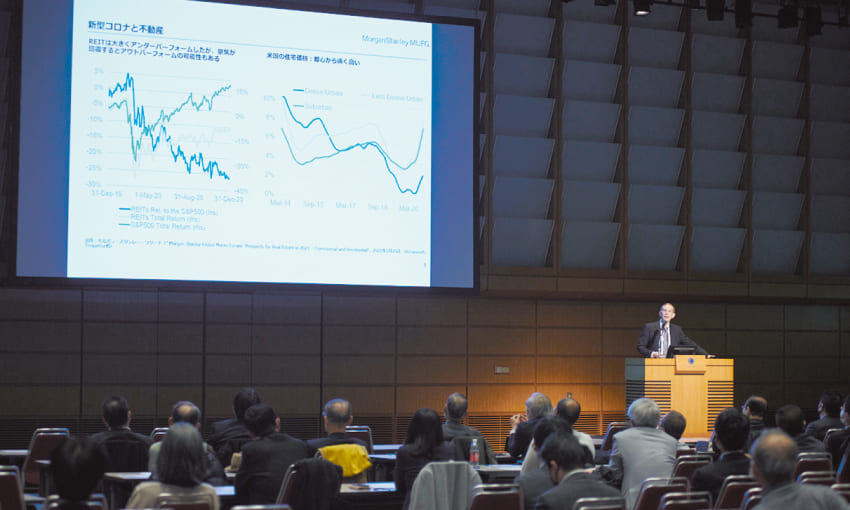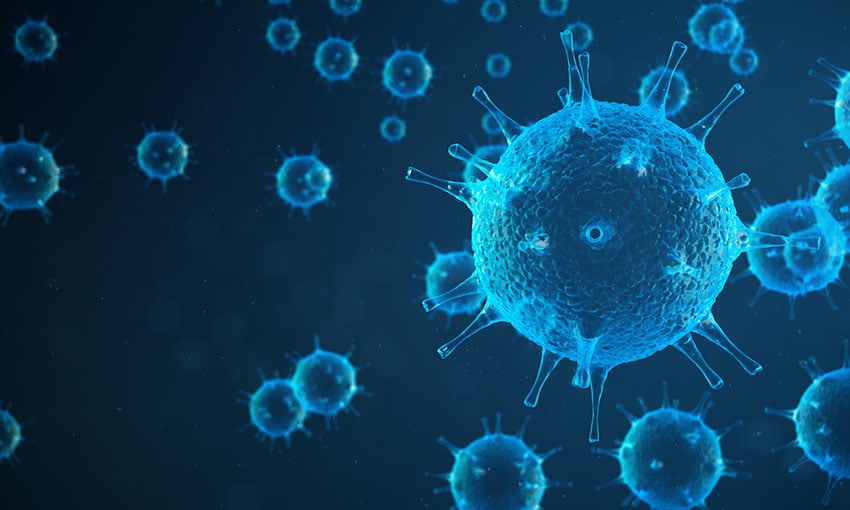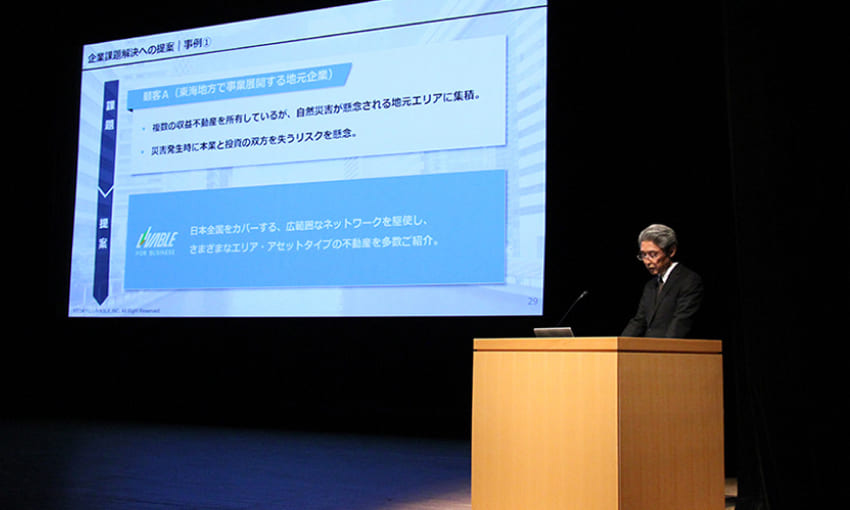シェアリングエコノミーが拓くCRE戦略の新境地|遊休不動産の価値最大化とワークプレイスの創造
#事業用不動産
#有効活用
#老朽化・遊休不動産
#ESG

近年、急速に成長するシェアリングエコノミーは、企業のCRE戦略においても新たな可能性を切り開いています。
CRE戦略においては、所有する不動産価値の最大化が最上位の課題です。その一方で、長期的に活用されていない遊休不動産は、維持管理コストや税負担といった経営上の大きなリスクとなり、この課題解決の大きな障壁となっています。
こうした課題に対して、シェアリングエコノミーは包括的な解決策を提供する有力な手段として注目されています。
今回は、シェアリングエコノミーの全体像から、不動産領域での具体的な活用法、そして導入にあたって検討すべきポイントまで網羅的に解説します。
資産価値を最大化するための不動産戦略をサポート
売却・査定について
目次
1. 企業がシェアリングエコノミーに取り組むべき背景

シェアリングエコノミーとは、個人や企業が所有している「活用可能な資産」を、インターネット上のプラットフォームを介して共有・交換する経済活動のことです。ここでいう資産とは、空間、モノ、スキル、移動手段など多岐にわたります。
空き部屋を貸し出す民泊や、使っていない車を貸し出すカーシェアリング、個人の専門スキルを販売するクラウドソーシングなど、さまざまなサービスが日々生まれており、これらのサービスに共通するのは、既存の資産を効率的に活用し、新たな価値を創造するという考え方です。
シェアリングエコノミーの市場規模は、この数年で急速に拡大しています。シェアリングエコノミー協会の調査によると、2024年度の国内市場規模は3兆1,050億円に達し、2022年度比で18.7%増加しました。
このペースで成長が続いた場合、2032年度には8兆5,770億円に達すると推計されています。また、市場の成長阻害要因がすべて解決したベストシナリオだと、15兆1,165億円まで拡大すると予測されています。
この急成長の背景には、エンドユーザーのニーズの変化があります。従来のように高額な購入費用を負担したり、定額制サービスに加入したりするよりも、「必要なときに、必要なだけ」利用できることを重視するユーザーが増えているのです。
実際の利用量に応じてコストを支払うため、無駄な出費を抑えられる費用対効果の高さも、多くの方に支持される理由となっています。
こうした市場の拡大を背景に、企業にとってもシェアリングエコノミーは見逃せない領域となっています。企業がシェアリングエコノミーを意識すべき理由は、そこに「新たなビジネス機会」と「企業の課題解決」の可能性が秘められているからです。
とくに、従来の不動産利活用や運営手法では解決が難しかった課題に対し、シェアリングエコノミーは新しい答えとなる可能性があります。既存資産の有効活用により新たな収益源を創出できるほか、「所有から利用」へと変化する価値観に沿ったビジネスモデルを構築することで、企業の社会的責任(CSR)の実現にも寄与します。
こうした取り組みは企業の社会的価値向上という副産物にもなり得ます。所有する空間をシェアすることで資源の有効活用につながり、ESG経営への貢献を通じて企業のブランドイメージ向上を実現できます。
関連記事:企業不動産を活用したストックビジネスが注目される理由
出典:情報通信総合研究所「シェアリングエコノミー関連調査2024年度調査結果」
出典:シェアリングエコノミー協会「シェアリングエコノミー市場調査 2022年版」
1.1. 不動産におけるシェアリングエコノミーについて
多くの企業が抱える課題のひとつに、遊休不動産の存在があります。これらの資産は、固定資産税や管理コストがかかる一方、収益を生み出さない「固定遊休資産」として企業経営を圧迫してきました。
しかし、シェアリングエコノミーは、この状況を一変させる可能性を秘めています。遊休不動産を一時利用のユーザーに貸し出すことで「収益資産」へと転換できるほか、限られたスペースの有効活用により地域コミュニティに新たな価値を提供することが可能です。
例えば、空きオフィスを時間貸しのコワーキングスペースとして提供し、スタートアップ企業や在宅ワーカーを支援したり、空き家を民泊施設として運用し、地域への観光客誘致や地方活性化に寄与したりする方法です。これらの取り組みは新たな収入源を生み出すだけでなく、企業の持続可能な経営姿勢を示すESGの観点からも評価されるでしょう。
関連記事:遊休不動産は積極活用すべし!具体的な事例と併せて解説
2. 不動産シェアリングエコノミーの提供形態とビジネスモデル

不動産シェアリングエコノミーは、その提供形態によっていくつかのタイプに分類されます。
| 提供タイプ | 提供者 | 利用者 | サービス例 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| CtoC型 | 個人 | 個人 | 民泊 | ・プラットフォームを介して利用 ・参入ハードルが低い ・品質や安全性の担保が課題 |
| BtoC型 GtoC型 |
企業や自治体 | 個人 | コワーキングスペース レンタルオフィス |
・サービス品質が高い ・既存事業とのシナジー効果が期待できる ・CRE戦略として検討しやすい |
| BtoB型 | 企業 | 企業 | 倉庫シェア サテライトオフィス |
・長期契約化や規模が大きいため、安定した収益源となりやすい ・企業ニーズに対応するためのカスタマイズも視野 |
CtoC型は、個人が所有する不動産を別の個人に貸し出すモデルで、代表的な例として民泊が挙げられます。このモデルの特徴は、プラットフォーム事業者が仲介役となり、個人同士の取引を支援する点にあります。参入のハードルは比較的低い一方で、個人による品質管理や安全性の確保が課題となることもあります。
BtoCやGtoC型は、企業や自治体が所有する不動産を個人に貸し出すモデルで、コワーキングスペースやレンタルオフィスがこれにあたります。企業や自治体が運営主体となるため、安定したサービス品質と信頼性を提供できる点が強みです。また、自社の既存事業との連携による相乗効果も期待できるため、CRE戦略としては最も検討しやすいモデルと言えるでしょう。
BtoB型は、企業が保有する不動産を別の企業に貸し出すモデルで、倉庫シェアやサテライトオフィスとして利用されるスペースなどがあります。企業間取引のため契約期間や利用規模が大きくなる傾向があり、安定した収益源となりやすい特徴があります。ただし、企業のニーズは多様化しており、柔軟なカスタマイズ対応が求められる場合も多く見られます。
これらの形態はいずれも「不動産という固定資産を必要なときにだけ利用したい」というニーズに応えるものであり、不動産シェアリングエコノミーは現代のビジネス環境に非常になじみやすいと言えるでしょう。
2.1. 不動産シェアリングの主要カテゴリとサービス例
現在、不動産シェアリングエコノミー市場では、さまざまなサービスが提供されています。
1.コワーキングスペース・シェアオフィス
コワーキングスペース・シェアオフィスは、フリーランスやスタートアップ企業、大企業のサテライトオフィスとして、多様な働き方に対応したワークスペースです。料金体系は月額1〜5万円、時間単位300〜500円などと柔軟に設定されています。高速Wi-Fiやプリンターなどの基本設備に加え、交流イベントやコミュニティ形成をサポートする付帯サービスも充実している点が特徴です。
2.民泊・宿泊サービス
民泊・宿泊サービスは、個人の住宅や企業の所有する物件を宿泊施設として提供するものです。民泊新法(住宅宿泊事業法)による180日制限や旅館業法、特区民泊など、複数の法律によって厳格な規制が設けられています。
ただし、この180日制限は届出住宅ごとに適用されるため、複数物件を所有する事業者であれば、各物件でそれぞれ年間180日間の営業が可能となります。参入時には十分な法的検討が必要となりますが、適切な運営により安定した収益が期待できる分野です。
3.そのほかの専門特化型サービス
倉庫シェアでは従量課金制による柔軟な料金設定、高級サービスアパートメントでは月額30〜80万円でのフルサービス提供、駐車スペースシェアでは時間単位数百円からの手軽な利用が可能となっています。これらのサービスは、特定のニーズに特化することで差別化を図り、安定した顧客層を獲得している点が共通しています。
また、専門代行業者の登場も注目すべき動向です。時間貸しで不要になったスペースの貸し出しを専門的に代行する業者が現れており、オーナーに代わってスペースの管理、予約受付、清掃、トラブル対応などを一手に担っています。これにより、オーナーの運営負担を大幅に軽減しつつ、効率的な収益化を実現する新たなビジネスモデルが確立されつつあります。
こうした専門事業者の参入は、不動産シェアリングエコノミー市場の成熟化を示すとともに、より多くの企業や個人にとって参入しやすい環境が整いつつあることを物語っていると言えるでしょう。
関連記事:拡大する民泊市場の可能性|法規制、収益構造と投資戦略
3. 企業が不動産シェアリングエコノミーに参入するメリットと課題

不動産シェアリングエコノミーへの参入は、収益・事業・ブランディングなど多方面でメリットをもたらします。一方で、把握しておくべきリスクや課題も存在するため、両者をふまえて自社の戦略に取り入れるかを検討しましょう。
3.1. 企業が得られる具体的なメリット
シェアリングエコノミーへの参入は、企業に多面的なメリットをもたらします。
収益面では、これまで収益を生まなかった遊休不動産から新たな収益を獲得できます。時間単位や日単位での貸し出しにより、長期契約よりも高い収益率を実現できる場合があるほか、景気変動や市場変化に対するリスクヘッジとしての効果も期待できるでしょう。
また、活用されていない不動産を収益資産に変えることで、保有コストを削減し、企業の資産効率(ROE)を向上させることが可能です。そのほか、資産の有効活用による生産性改善(ROA)にも寄与し、株価評価(PBR)の向上へとつながる可能性があります。負担となっていた固定資産を安定した収益源へと転換できる点は、企業にとって大きな魅力です。
事業面においては、利用者の行動データや嗜好データを収集・分析することで、既存事業のマーケティング戦略や商品開発に活用できる貴重な市場情報を獲得できます。また、利用者コミュニティの形成により口コミ効果やネットワーク効果が生まれ、持続的な競争優位性を構築できる点も重要なメリットです。
ブランド面では、遊休不動産の活用は単なる収益化に留まりません。既存建物を再利用することで環境負荷を低減し、シェアオフィスやコワーキングスペースといったサービスを通じて多様な働き方を支援することは、企業が社会的な課題解決に貢献する姿勢を示すことになります。
こうした取り組みは、資源の有効活用や地域貢献に取り組む姿勢として高く評価され、社会貢献意欲の高い企業としてステークホルダーからの信頼度向上に寄与するほか、ESG経営として投資家からも高く評価されるでしょう。
そのほか採用活動においても競争優位性を生み、優秀な人材の獲得にも好影響をもたらすことも期待できます。
関連記事:ESG経営と不動産~環境、社会、ガバナンスの観点での経営と不動産の関連性~
3.2. 企業が検討すべきデメリットやリスク
魅力的なメリットがある一方で、不動産シェアリングエコノミーには注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが成功への鍵となるでしょう。
収益性の課題として、市場の成長に伴い類似サービスが増加し、レッドオーシャン化する可能性があります。価格競争に陥ると収益性が急速に低下する恐れがあるほか、プラットフォーム手数料や運営システムの維持費用など、従来の不動産事業では発生しなかった継続的なコストが収益を圧迫するリスクもあります。
既存事業とのカニバリゼーション(共食い)も重要な懸念材料です。ホテル事業と民泊事業、オフィス賃貸とコワーキングスペースなど、顧客層が重複することで既存事業の顧客を奪ってしまう可能性があり、明確な差別化戦略が不可欠です。
信頼性と品質管理の課題では、プラットフォームを介して不特定多数のユーザーと接するため、個人情報漏洩やセキュリティ侵害のリスクが伴います。また、多様なユーザーニーズに対応しながら一定の品質を維持することは容易ではなく、サービス品質のばらつきによるブランドイメージの低下も懸念されます。
3.3. 不動産シェアリングエコノミーの課題と対策
参入を検討する際には、前述のリスクを回避するための具体的な対策を講じる必要があります。
まず重要なのが、法規制への適切な対応です。事業内容によって法規制の遵守が求められるため、専門家に相談し、適切な許認可を事前に取得しておきましょう。これにより事業の信頼性を高め、予期せぬトラブルを回避できます。
運営面では、顧客対応や予約管理、清掃など専門性の高い業務の発生によるリソースの問題があります。外部の専門業者への委託や既存管理部門との連携により、効率的な運営体制を構築することが賢明でしょう。
また、利用者の個人情報保護とシステムセキュリティの確保も重要です。専門部署や専門企業と連携するなど、強固なデータ管理体制を構築し、定期的なセキュリティ監査を実施することが求められます。
既存事業を持つ企業にとってとくに注意が必要なカニバリゼーションの防止に関しては、ターゲットや価格帯を明確に区分し、既存事業の補完的なサービスとして位置づけることで、相乗効果を生み出すことができるでしょう。
4. 不動産シェアリングエコノミー参入戦略と実践的ポイント

不動産シェアリング事業を成功させるためには、参入前の検討段階で以下の重要なポイントを見極めることが重要です。
●どの物件がシェアリングエコノミーに適しているか
保有物件の適性評価において最も重要なのは、「時間軸での遊休不動産」を戦略的に選定することです。
この選定が重要な理由は、既存事業に支障をきたすことなく、確実な収益向上を実現できるからです。平日夜間や休日に空いているスペース、稼働率の低い施設など、時間的・空間的な遊休状態が発生している物件であれば、本業への影響を最小限に抑えながらシェアリング化を進められます。
物件特性を評価する際は、想定するサービス形態に応じて判断することが大切です。都市部でコワーキングスペースを展開するなら駅からのアクセス性、郊外で倉庫シェアを考えているなら物流拠点としての利便性、住宅地で民泊を検討する場合は観光地へのアクセスや住環境といったように、用途別の評価軸を使い分ける必要があります。
最も重要なのは、既存事業への影響を考慮した優先順位付けです。コアビジネスで常時使用している施設は避け、年に数回しか使われない施設や特定時間帯のみ利用される空間から着手することで、着実にシェアリング化による収益向上を実現できます。
●市場はどのような状況か
ターゲット顧客の具体的ニーズを深掘りし、自社の差別化ポイントを明確にすることが重要です。エリアの就業者数やテレワークの普及率といった定量データに加え、潜在的な利用者がどのような課題を抱え、何を求めているかを定性的に把握することで、独自性のあるサービス設計が可能になります。
競合分析では、料金水準や提供サービスの比較に加え、各施設の稼働率や利用者の満足度、運営上の課題まで詳細に調査することで、競合が見落としている市場のニーズや改善点を発見できます。
●法的規制への事前対応は十分か
不動産シェアリング事業では、どのようなサービスを提供するかによって適用される法規制が変わるため、事業開始前の法的確認が欠かせません。
例えば、民泊事業なら住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法、コワーキングスペースを運営する場合は建築基準法や消防法への対応が必要となります。とくに注意したいのは、既存建物を別の用途で使うときの手続きです。建築確認申請や用途変更の手続きが求められることが多く、完了まで数ヶ月かかることも珍しくありません。
何より大切なのは、サービス開始前に必要な許可をすべて取得し、運営開始後も法令を遵守できる体制を作っておくことです。法的な問題を見逃してしまうと、あとから大規模な工事が必要になったり、最悪のケースでは事業を停止せざるを得なくなったりする恐れがあるからです。
こうしたリスクを避けるためにも、専門家に相談し、丁寧な事前チェックを心がけましょう。
●事業参入形態は自社の方針に適しているか
自社の既存事業との相乗効果を最大化できる方式を見極めることが重要です。直営方式では自社でコントロールできる範囲が広い反面、運営負担も大きくなります。フランチャイズ加盟では実績のあるノウハウを活用できる一方、運営方針の制約を受けることになります。
初期投資を抑えたい場合は既存プラットフォームへの物件掲載、安定収入を重視するならサブリース方式、部分的な負担軽減なら業務委託方式といった選択肢があります。どの方式を選択するかよりも、選択した方式で既存事業とのシナジーを生み出せるかどうかが重要な判断基準となります。
このように、自社の経営戦略全体のなかでシェアリング事業をどう位置づけ、既存事業との相乗効果をいかに生み出すかという視点で運営方式を選択することが、持続的な成功のポイントとなるでしょう。
4.1. 成功・失敗事例から学ぶ実践知
不動産シェアリングエコノミーの成功には、理論だけでなく実践的なノウハウが不可欠です。ここでは、具体的な事例から学ぶべきポイントを紹介します。
まずは成功事例から見ていきましょう。
成功事例1:高級シェアオフィスの差別化戦略
大手グループが展開するシェアオフィス事業では、駅直結の好立地と高級感のある内装、充実したサービスで高いブランド力を確立しています。この成功の鍵は、単なる作業場ではなく「新しいビジネスの創造の場」という価値提供で明確な差別化を図り、価格競争に巻き込まれない独自のポジションを築いたことにあります。
成功事例2:サービスアパートメントの市場創造
コロナ禍で稼働率が80%台から10%台まで落ち込んだ高級ホテルが、「ホテルに住む」というコンセプトのもと、使われていない客室を活用したサービスアパートメント業を開始しました。予約開始からわずか4時間で完売となり、想像以上の成果を出しました。
当初はビジネス利用を想定していましたが、実際には「高級ホテル体験をリーズナブルな価格で味わいたい」というプライベート利用のニーズが予想以上に多く、この成功を受けてほかの大手ホテルも追随する形となり、新たな市場を創造することに成功しました。
失敗事例1:コミュニティ機能への過大投資
コワーキングスペースブームが地方都市でも広がった際、「人が集まればそこで仕事が生み出される」という期待から、ビル1棟を借りてオープンした事業者がありました。しかし、運営者も入居者も同様の期待を持っていたため、実際には仕事らしい仕事を生み出せず、仕事を期待していた利用者は自然と離れていき、結果として借金だけが残り閉店となりました。
利用者が求めていた仕事の増加やスキルアップといった具体的な成果を、運営側が汲み取れなかったことが敗因となっています。
失敗事例2:大手企業との競争敗北
資本力のある大手企業が展開する投資的サービスとの品質・価格競争に敗北した事例があります。世界的企業や地場の大手が超一等地で大規模なスペースを展開しているなかで、IT大手企業や行政主導で無料のコワーキングスペースを開放する動きも加速しており、独自性のないサービスでは競争に勝つことは困難でした。
成功事例を分析すると、他社との明確な差別化と市場の潜在的なニーズを正確に捉えることが成功の要因であることがわかります。対照的に、失敗事例では、マーケットニーズの読み違いや大手企業との競争が失敗を招いています。
このように、成功事例では明確な差別化戦略と潜在ニーズの的確な把握が鍵となります。失敗事例では思い込みによる運営やニーズの見誤り、大手との無謀な競争が明暗を分けています。これらの教訓を踏まえて、次章では実際にシェアリングエコノミーに参入する際には、どのような戦略で進めていけば良いのかを確認しましょう。
4.2. 不動産シェアリングエコノミー参入における戦略
事例から得られる教訓を踏まえ、現実的な導入・展開戦略を構築することが重要です。
まず、段階的導入によるリスク管理が成功の出発点となります。過度な期待は禁物であり、まずは小規模に事業を開始し、市場の反応を慎重に検証することが重要です。現実的な収益計画と明確な撤退ラインを設定しておくことで、リスクを最小限に抑えながら事業の妥当性を見極められます。
既存事業との戦略的連携は、単体での収益化が困難なシェアリング事業においてとくに重要です。無人運営システムの活用や既存の管理・清掃体制との統合により、運営効率を向上させることができます。本業との相乗効果を創出できるビジネスモデルを検討し、事業単体での黒字化が困難でも企業全体としてメリットを生み出すことが重要です。
持続可能性を重視した運営体制の構築では、長期的な競争優位性の確立を目指します。ユーザーコミュニティの活性化を促しつつも、既存利用者だけで固まってしまわず、新しい利用者が入りやすい環境を維持することが重要です。付帯サービスによる収益多角化も検討し、運営方式についても自社の経営資源に応じて最適な形態を選択することが成功への鍵となります。
こうした取り組みを一歩ずつ進めることで、リスクを抑えながら着実にシェアリングエコノミーのメリットを得て、遊休不動産を企業の成長に役立つ資産へと変えることができるでしょう。
5. 遊休不動産の価値創造につながるシェアリングエコノミー

この記事では、企業が不動産シェアリングエコノミーに取り組むべき背景から、具体的な参入方法、成功へのポイントまでを解説しました。
ただし、成功のためには市場動向の把握、自社保有物件の適性評価、現実的な事業計画の策定が不可欠です。成功事例と失敗事例の分析からも明らかなように、過度な期待を排し、データに基づいた段階的なアプローチが重要となります。
シェアリングエコノミーに取り組む際は、自社の保有物件の適性評価から始めてみてください。
宅地建物取引士
佐藤 賢一 氏
Kenichi Sato
大学卒業後、不動産業界一筋。賃貸仲介・管理から売買仲介まで幅広い実務を経験した後、専門性を深め、プライム企業にて信託関連のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務に従事。
現在は注文住宅会社の不動産部門責任者を務めつつ、多様な経験を活かし兼業ライターとしても活動中。不動産の実務から投資・管理戦略まで、多角的な視点に立ったわかりやすい解説を得意としています。
※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。
関連記事
Moved Permanently
The document has moved here.